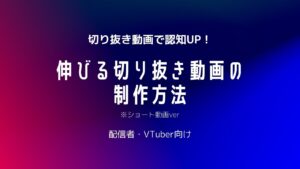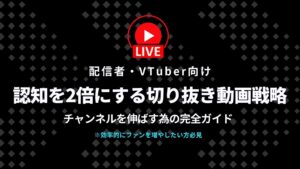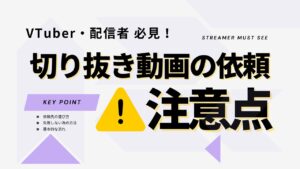医院の「集客にSNSは必要?」TikTok運用などクリニックの動画活用は今からでは遅い?

「SNSで集客している医院が増えているけど、うちの医院は出遅れてしまったかな…」
「今から動画を始めても効果はあるのだろうか…」
と考えている医院関係者も多いのではないでしょうか?
医療機関のSNSマーケティングは、これからが本番という状況です。
他院との差別化を図るには、今がSNS活用を始める絶好のタイミングといえるでしょう。
この記事では、医療機関のSNS戦略に悩む方に向けて、
- SNSを活用した効果的な集客方法
- 動画コンテンツの作り方のポイント
- 患者さんとの信頼関係構築のためのSNS運用術
上記について、医療機関向けの動画マーケティングディレクターとしての経験を交えながら解説しています。
SNSを活用した集客は、決して難しいものではありません。
しっかり戦略を組められると、今から始めても十分な効果が期待できるので、ぜひ参考にしてください。
あなたがSNSや動画活用で集客したいのであればユニセントへ一度お問い合わせいただくのがおすすめです。
ユニセントはSNSに特化した動画制作・マーケティングを行なっており、1動画あたり最短1週間で企画・制作・投稿まで完了します。
今なら30分の無料相談もご用意しているので、SNS集客・動画マーケティングに興味がある人はぜひお問い合わせください。
https://unisent.co.jp/contact/
今なら医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
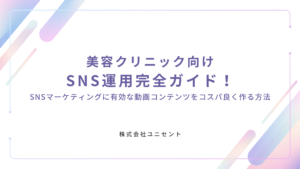
医院がSNSを活用するメリット

医院のSNS活用は、効果的な集患と患者様とのコミュニケーション強化に大きな可能性を秘めています。
SNSを活用することで、医院の認知度向上やブランディングはもちろん、患者様との信頼関係構築にも役立てることができるでしょう。
具体的には、診療時間の変更や休診のお知らせ、予防接種の案内、健康や美容に関する情報発信など、患者様にとって有益な情報を無料で発信できます。
SNSの活用は、医院の規模に関係なく、誰でも始めることができるツールです。
特に若い世代の患者様は、医院選びの際にSNSでの情報収集を行うことが一般的になってきました。
以下で、SNS活用における具体的なメリットを詳しく解説していきます。
無料で利用できる
SNSは医院にとって、初期費用をかけずに情報発信できるツールです。
YouTubeやInstagram、TikTokなどのSNSプラットフォームでは動画投稿など無料で可能です。
広告費を抑えながら集患につなげられる点は、特に開業したての医院にとって大きなメリットとなるはずです。
SNSの有料広告を活用する場合でも、新聞やテレビCMと比べてより詳細なデータが得られる、という点ではより費用対効果を見込めるでしょう。
運用に必要なのは、スマートフォンやパソコンといった一般的な機器だけ。
専用の撮影機材がなくても、スマートフォンのカメラで十分な品質の写真や動画を撮影できます。
リソースに余裕があるなら、医院のスタッフが空き時間を使って投稿を作成することで、外注コストも抑えられるでしょう。
SNSマーケティングの基本的なノウハウは、インターネット上の無料記事やYouTube動画で学べます。
経験を積みながら、徐々にスキルアップを図り集患に繋げていきましょう。
認知とブランディングの向上から集患が期待できる
SNSを活用することで、医院の認知度向上とブランド価値の確立が期待できます。
YouTubeやInstagram、TikTokなどのSNSプラットフォームでは、医院の特徴や診療方針を効果的に発信することが可能でしょう。
実際に、SNSを積極的に活用しているクリニックでは、フォロワー数が1年で数万人増加した事例も存在します。
医院の雰囲気や施設の清潔感を写真や動画で伝えることで、来院前の不安を軽減させる効果も。
さらに、定期的な情報発信により、地域住民との信頼関係構築にも役立ちます。
一方で、医療機関のSNS活用では、投稿内容に関する規制を遵守する必要があります。
医療法や医療広告ガイドラインに沿った情報発信を心がけましょう。
医療広告ガイドラインはこちらをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
患者様の興味を引く健康情報や予防医療に関する知識の共有は、フォロワー数増加に効果的な手段となるはずです。
定期的な投稿と質の高いコンテンツ制作により、長期的な集患効果が見込めます。
SNSマーケティングを成功させるには、継続的な運用体制の構築が重要なポイントとなっています。
リアルタイムに告知・サービス紹介ができる
SNSを活用することで、医院の最新情報をタイムリーに発信できます。
インフルエンザの流行状況や診療時間の変更、新しい医療機器の導入など、患者様に役立つ情報をすぐにお届けすることが可能でしょう。
YouTubeやInstagram、TikTokでは、写真や動画を活用して視覚的にわかりやすく伝えられるのが特徴的です。
特に緊急性の高い情報は、SNSを通じて素早く広範囲に周知できるメリットがあります。
例えば、台風による休診や診療時間の変更といった急な変更にも柔軟に対応できました。
医院のイベントや健康セミナーの告知も効果的に行えるのがSNSの強みです。
予防接種の受付開始や各種検診の案内など、季節に応じた医療サービスの情報発信が可能になりました。
投稿内容に合わせて適切なキーワードやハッシュタグを付けることで、より多くの方々への情報到達が期待できます。
さらに、投稿に対する反応や共有数を確認できるため、どのような情報に患者様が興味を持っているのか把握することも容易になるでしょう。
この分析結果を活かして、より効果的な情報発信が実現できます。
患者様とのコミュニケーションツールになる
SNSを通じた患者様とのコミュニケーションは、医院の信頼性向上に大きな効果をもたらします。
YouTubeやInstagram、TikTokのコメントやDM機能を活用すれば、診療時間外でも気軽に質問や相談を受け付けることが可能でしょう。
特に若い世代の患者様は、電話よりもSNSでのコミュニケーションを好む傾向にあります。
定期的な情報の発信は、フォロワーとの関係構築に役立ちます。
例えば、インフルエンザの流行時期には予防接種の案内を、花粉症のシーズンには対策情報を共有することで、医院としての専門性をアピールできるのです。
また、診療所のスタッフ紹介や日常の様子を投稿することで、来院前の不安を和らげる効果も期待できます。
医院の雰囲気が伝わる投稿は、新規患者の獲得にも効果的な手段となっています。
さらに、予約システムとSNSを連携させることで、診療予約の利便性を高めることも可能です。
患者様の利便性向上は、リピート率の上昇にもつながりましょう。
医院がSNSを活用するデメリット

医院のSNS活用には、注意すべきデメリットがいくつか存在します。
これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることで、効果的なSNS運用が可能となるでしょう。
SNS運用には、アカウントの日々の更新や投稿内容の企画、患者様からのコメントへの返信など、相応の時間と労力が必要となります。
専門的な知識がないと、投稿内容の質が低下したり、医療広告ガイドラインに抵触するリスクも生じてしまいます。
また、SNSでの集患効果を実感するまでには、半年から1年程度の期間を要することも珍しくありません。
投稿を継続的に行わないと、フォロワー数の増加やエンゲージメントの向上は期待できないのです。
さらに、投稿内容や返信コメントによっては、予期せぬ炎上を引き起こす可能性もあります。
医療機関という性質上、一度炎上が発生すると、信頼回復には多大な時間と労力を要することになってしまうでしょう。
以下で、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
アカウント運用に知識や時間が必要
SNSの運用には専門的な知識やスキルが求められます。
投稿の企画から撮影、編集、そして効果測定まで、多岐にわたるタスクをこなす必要があるでしょう。
医療機関では診療が最優先となるため、SNS運用に十分な時間を確保することが困難な状況です。
特に医療機関のSNS運用では、医療広告ガイドラインへの理解が不可欠となりました。
投稿内容が規制に抵触していないか、細心の注意を払う必要があります。
また、個人情報保護の観点から、写真や動画の取り扱いにも慎重さが求められるのが現状です。
運用担当者には、医療の専門知識に加えてSNSマーケティングのスキルも必要になってきます。
YouTube、Instagram、TikTokなど、それぞれのプラットフォームの特性を理解し、適切なコンテンツを制作する能力が重要なポイント。
医院によっては、外部の専門家に運用を委託することも検討に値する選択肢となっています。
SNSの効果的な運用には、継続的な学習と情報収集が欠かせません。
SNSマーケティングの最新トレンドやアルゴリズムの変更にも常に目を光らせる必要があるでしょう。
長期的に継続をする必要がある
SNSの運用は長期的な視点で取り組む必要があります。
患者様との信頼関係を築くには、最低でも6か月から1年以上の継続的な発信が求められるでしょう。
医療機関のSNSアカウントは、投稿が途絶えると、フォロワーの離脱やエンゲージメント(いいね数やコメント数)の低下につながってしまいます。
投稿頻度は、最低でもInstagramなら週3回以上、YouTubeは月4本以上が理想的です。
ただし、医院の規模や人員体制によって、無理のない範囲で設定することがポイント。
SNSの運用担当者を明確にし、投稿スケジュールを事前に組んでおくと継続的な発信が可能です。
医院によっては外部に動画制作やSNSマーケティングを依頼するケースも増加中。
継続的な運用体制を整えることで、患者様との長期的な関係構築が実現できるはずです。
結果が出るまでに時間がかかる
SNSを活用した医院の集患は、成果が表れるまでに一定の時間を要します。
最低でも6か月から1年程度の継続的な運用が必要でしょう。
フォロワー数の増加や投稿への反応は、徐々に上向いていく傾向にあります。
SNSのアルゴリズムは、アカウントの信頼性を判断するため、投稿の頻度や質、エンゲージメント(いいね数やコメント数)などを重視。
そのため、フォロワーとの信頼関係構築には、地道な情報発信の積み重ねが欠かせません。
医療機関のSNSマーケティングでは、月間4〜8本程度の投稿を6か月以上継続することで、徐々に成果が見え始めてきました。
特に、診療科目や症状に関する専門的な情報発信は、時間をかけて患者様からの信頼を獲得できる有効な手段となっています。
一朝一夕には結果が出ないものの、長期的な視点で取り組むことで、確実な成果につながるSNSマーケティング。
医院の特色や強みを活かした継続的な情報発信が、成功への近道といえるでしょう。
炎上のリスク
SNSでは、一度投稿した内容が瞬時に拡散されるため、医院の評判に大きな影響を及ぼす可能性があります。
過去には、某医院のスタッフが不適切な投稿を行い、わずか数時間で全国的な批判に発展した事例も存在しました。
SNS運用では、医療法や個人情報保護法に違反する投稿を避けることが絶対条件でしょう。
特に患者様の写真や症例写真を掲載する際は、明確な同意を得る必要があるのです。
また、医療機関としての品位を損なう投稿や、誤解を招く表現は厳に慎まなければなりません。
投稿前には必ず複数人でチェックする体制を整えることをお勧めします。
万が一炎上が発生した場合は、迅速な謝罪と対応が重要となるため、事前に危機管理マニュアルを作成しておくべきです。
SNSの特性を理解し、慎重な運用を心がけましょう。
医院のSNS活用方法

医院のSNS活用は、戦略的なアプローチと明確な目的意識が成功への鍵となります。
SNSを効果的に活用するためには、医院の特色や強みを活かしながら、患者様のニーズに合わせた情報発信を心がける必要があるでしょう。
特に、診療科目や得意分野に関連した健康情報の提供、予防医療のアドバイス、季節性の疾患に関する注意喚起、トレンドの美容情報など、患者様の日常生活に役立つ情報を定期的に発信することが重要です。
こちらの記事でも媒体別にSNS運用のポイントを詳しく解説しています↓
https://unisent.co.jp/douga_marketing_sns_biyouclinic1/

具体的には、インフルエンザの流行時期における予防接種の案内や、花粉症シーズンでの対策方法の紹介、生活習慣病予防のためのアドバイスなど、タイムリーな情報提供が効果的でしょう。
また、医院のスタッフ紹介や施設案内、新しい医療機器の導入情報なども、患者様との信頼関係構築に役立ちます。
以下で、具体的なSNS活用方法について詳しく解説していきます。
患者様にとって有意義な情報を発信する
医院のSNS活用において、患者様に有意義な情報を発信することは最も重要なポイントです。
季節性の疾患に関する予防法や、健康や美容管理のアドバイスなども患者様の関心が高い内容となっています。
医院のスタッフ紹介や施設の案内写真を投稿することで、来院前の不安を和らげる効果も期待できます。
ただし、投稿内容は医療広告ガイドラインに沿って、誇大広告や比較広告を避ける必要があるため、慎重な判断が求められます。
患者様からの質問やコメントには、個人情報に配慮しながら、丁寧に対応することが大切なポイントとなっています。
医療広告ガイドラインを守る
医療広告ガイドラインの遵守は、医院のSNS運用において最重要事項です。
厚生労働省が定める医療広告ガイドラインでは、SNSでの投稿内容に厳格な制限が設けられています。
医療広告ガイドラインはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
治療の前後写真や、特定の治療効果を強調する表現は禁止されているでしょう。
医院のSNS投稿では、医師の経歴や専門分野、保有する医療機器の紹介など、事実に基づいた情報発信に留めることが大切になりました。
また、患者様の体験談やカスタマーレビューの掲載も規制対象となっています。
医療法改正により、2018年6月からWebサイトやSNSも医療広告の規制対象に含まれることになりました。
違反した場合は、業務停止などの行政処分の対象となる可能性も。
SNSでの情報発信は、医療機関の専門性や信頼性を伝える絶好の機会となります。
ただし、投稿内容が医療広告ガイドラインに抵触していないか、細心の注意を払う必要があるでしょう。
定期的なガイドラインの確認と、投稿前の内容チェックを欠かさず行いましょう。
SNSの種類と特徴

医院のSNS活用において、各プラットフォームの特性を理解し、適切に使い分けることが重要です。
それぞれのSNSには独自の利用者層や特徴があり、医院の発信したい情報や目的に合わせて選択することで、効果的な情報発信が可能となります。
医院が活用できる主なSNSプラットフォームには、YouTube、Instagram、TikTokなどがあります。
以下で、各SNSの具体的な活用方法について詳しく解説していきます。
YouTubeの活用方法
YouTubeは医院のSNS活用において、非常に効果的なプラットフォームです。
医院の特徴や施術内容を動画で分かりやすく伝えることができ、視聴者の信頼獲得に繋がります。
具体的な活用例として、院長による治療説明や施術の流れ、スタッフ紹介などのコンテンツが挙げられましょう。
実際に、歯科医院のYouTubeチャンネルで月間10万回以上の視聴を獲得している事例も存在します。
動画は文字や画像と比べて情報量が多く、視聴者の理解度を高めることが可能です。
YouTubeの特徴として、Google検索結果に動画が表示されやすい点も見逃せません。
適切なSEO対策を行うことで、医院の認知度向上に大きく貢献するでしょう。
ただし、医療広告ガイドラインに沿った内容制作が必須となります。
患者様の不安を和らげる情報提供を心がけ、誇大広告は避けるべきです。
定期的な投稿と高品質なコンテンツ制作で、長期的な信頼関係構築を目指しましょう。
医院のYouTube活用についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓
https://unisent.co.jp/douga_marketing_yt_biyouclinic/

Instagramの活用方法
Instagramは多くのユーザーが利用する人気SNSプラットフォームです。
医院のInstagram活用では、診療前後の院内の様子や、スタッフの日常業務風景を投稿することで親近感を演出できましょう。
写真や動画を活用し、医院の雰囲気や清潔感を視覚的に伝えることが可能です。
特に、インスタグラムストーリーズを使えば、24時間限定で診療時間の変更やお知らせを手軽に発信できます。
ハッシュタグを効果的に活用することで、地域や症状に関心のある潜在患者にリーチすることができます。
例えば「#○○市」「#歯医者」といった地域特化型のタグは、集患に効果的でしょう。
医療機関のInstagramでは、投稿のほとんどが写真付きコンテンツとなっています。
診療室や待合室の清掃・消毒の様子、新しい医療機器の紹介など、患者の不安を和らげる投稿が効果的。
リール機能を使った15秒〜60秒程度の動画投稿も、エンゲージメント率向上に貢献するポイントとなるはずです。
TikTokの活用方法
TikTokは10代から20代の若年層を中心に爆発的な人気を誇るショート動画プラットフォームです。
医院のTikTok活用では、15秒〜60秒程度の短い動画で診療内容や施設の紹介を行うことが可能でしょう。
特に、歯科矯正や美容医療などの分野では、ビフォーアフターの変化を印象的に伝えられます。
TikTokの特徴的な機能である豊富なエフェクトやBGMを活用すれば、医療情報も親しみやすい形で発信できました。
投稿のコツは、トレンドを意識した演出や、医師・スタッフの人柄が伝わる内容作りにあります。
ただし、診療の様子を撮影する際は、患者のプライバシーに十分配慮する必要があるでしょう。
医療法や広告ガイドラインに沿った投稿を心がけましょう。
TikTokのアルゴリズムは、ユーザーの興味関心に合わせて投稿を表示する仕組みを採用。
そのため、的確なターゲット層へのリーチが期待できます。
定期的な投稿を続けることで、若い世代への認知度向上に効果的なツールとなるはずです。
こちらの記事では医院のショート動画活用について詳しく解説しています↓
https://unisent.co.jp/douga_shorts_sns_clinic/

医院が直面するSNS活用時の課題

医院のSNS活用において、多くの医療機関が実践段階で様々な課題に直面しています。
その背景には、医療機関特有の制約や、SNS運用に関する経験不足が大きく影響を及ぼしています。
医療広告ガイドラインの遵守が必要な中で、魅力的なコンテンツを作成することは容易ではありません。
例えば、診療所の様子を紹介する動画を作成する際も、患者のプライバシーに配慮しながら撮影を行う必要があるでしょう。
また、医師や看護師が本来の医療業務に専念する必要がある中で、SNSの運用に十分な時間を確保することも難しい現状です。
特に地方の診療所では、SNS運用のノウハウを持つスタッフの確保が困難なケースも少なくありません。
さらに、投稿内容の企画から実際の配信まで、一連の作業を担当できる人材を見つけることも容易ではないのが実情でしょう。
以下で、医院が直面する具体的な課題について詳しく解説していきます。
患者様に響かないコンテンツの発信
SNSで成功を収めている医院の多くは、患者様の悩みや関心事に寄り添ったコンテンツを発信しています。
一方で、医院側の一方的な情報発信に終始してしまうケースが散見されます。
患者様が求める情報と、実際に発信されているコンテンツにミスマッチが生じているのが現状でしょう。
特に多いのが、医療機器の性能や治療の専門用語を羅列するだけの投稿です。
確かに医療従事者にとっては重要な情報かもしれませんが、一般の患者様にとっては難解で遠い存在に感じられてしまいます。
効果的なSNS運用のためには、患者様目線でのコンテンツ作りが不可欠となっています。
例えば、症状の改善事例や日常生活でできる予防法、治療後の経過など、具体的でイメージしやすい情報が求められるでしょう。
医院のSNSアカウントのフォロワー数や投稿への反応を分析し、どのような内容が患者様の興味を引いているのか把握することが重要です。
データに基づいたコンテンツ戦略の立案が、SNS運用成功への近道となりました。
ノウハウ不足
SNSの運用には専門的な知識やノウハウが必要不可欠です。
医療機関特有の広告規制への理解も欠かせません。
SNSマーケティングの基礎知識や効果的な投稿方法を学ぶ時間を確保しなければなりません。
投稿内容の企画から実際の制作まで、多岐にわたるスキルが求められるでしょう。
- 写真や動画の撮影技術
- 編集ソフトの使い方
- コピーライティング
- SEO対策
- マーケティング
など、習得すべき項目は山積みです。
各SNSプラットフォームの特性や利用者層を把握することも重要なポイント。
YouTubeやInstagram、TikTokでは、求められる投稿の形式や内容が大きく異なってきます。
外部のSNSコンサルタントやマーケティング会社に運用を依頼するのも一つの手段でしょう。
ただし、医療機関の特性を理解している業者を選ぶ必要があるため、慎重な選定が求められます。
医療広告ガイドラインに精通したパートナー選びが成功の鍵となりましょう。
SEO対策ができない
SEO対策の実施には専門的な知識やスキルが必要不可欠でしょう。
多くの医院では、マーケティング担当者が不在のため、効果的なSEO対策を行うことができない状況に直面しています。
特に、GoogleのアルゴリズムアップデートやSEOの最新トレンドへの対応は、専門家でないと難しいものです。
医院のスタッフは本来の医療業務で多忙を極めており、SEO対策に時間を割くことが困難な現状があります。
また、SEOツールの選定や運用にも専門知識が必要となるため、適切なツールの活用もままならないことが多いでしょう。
さらに、コンテンツ制作においても、医療情報の正確性を担保しながら、SEOに最適化された記事を作成することは容易ではありません。
このような状況を改善するためには、外部のSEO専門家への相談や、SEOに特化したマーケティング会社との連携を検討する必要があるかもしれません。
SNSアカウントの分析・改善ができない
SNSアカウントの分析と改善は、医院のSNS運用において重要な課題です。
アカウントの投稿内容や反応を適切に分析できないことは、効果的なSNS運用の大きな障壁となっています。
各SNSプラットフォームには独自の分析ツールが用意されていますが、それらを使いこなせていない医院が多いのが現状でしょう。
例えば、Instagramのインサイト機能では、フォロワー数の推移やリーチ数、エンゲージメント率などの重要な指標を確認できます。
これらのデータを元に、投稿内容や投稿時間の最適化を図ることが可能となりました。
投稿内容の改善には、ターゲット層の反応や興味関心を把握することが不可欠です。
医院のスタッフが多忙な中、SNSの分析まで手が回らないケースも少なくありません。
そこで、外部の専門家やツールを活用することも一つの解決策となるはずです。
SNSマーケティングに特化したツール「SocialDog」や「Buffer」などを導入することで、効率的な分析と改善が可能になるでしょう。
SocialDogはこちら
https://social-dog.net/ja/
Bufferはこちら
https://buffer.com/
リソース不足によるSNS運用の限界
SNS運用を成功させるためには、適切な人材と時間の確保が不可欠です。
多くの医院では、日々の診療業務に追われ、SNSの更新に十分なリソースを割けないのが現状でしょう。
特に、専任のスタッフを置くことが難しい小規模医院では深刻な課題となっています。
SNSの運用には、コンテンツの企画から制作、投稿、エンゲージメント管理まで、様々な業務が発生します。
1日30分程度の作業時間でも、週に3回以上の更新を継続するのは容易ではありません。
また、質の高いコンテンツを作るには、撮影や動画編集のスキルも必要となるでしょう。
外部のSNS運用代行サービスを利用する選択肢もあります。
SNS運用代行サービスを利用する場合、30万円から100万円程度の費用が発生するため、投資対効果を慎重に検討する必要があるでしょう。
自院の規模や目的に合わせて、運用方法を見直すことが重要です。
リソース不足を補うためには、投稿頻度を下げる、テンプレートを活用する、スタッフで分担するなどの工夫が効果的。
継続できる範囲で無理のない運用を心がけましょう。
弊社、株式会社ユニセントでは月5万円から効果的なSNSコンテンツ制作と運用代行を行なっております。
あまり予算をかけずに手取り早くSNS運用をしたい、社内にリソースがない、という方は是非お気軽に無料お問い合わせをご利用ください。
御社にとって最適な運用プランをご提案いたします。
お問い合わせはこちら
https://unisent.co.jp/contact/
コンテンツクオリティの低下
SNSの活用には、質の高いコンテンツを継続的に発信することが求められます。
医療機関のSNS運用において、最も深刻な課題はコンテンツクオリティの低下でしょう。
多忙な医院スタッフが日々の投稿を続けるのは容易ではありません。
時間的制約から、安易な投稿や使い回しのコンテンツが増えてしまう傾向にあるのが現状です。
特に地方の中小規模の医院では、専任のSNS担当者を置くことが難しく、診療の合間を縫って投稿作業を行うケースが多いでしょう。
そのため、医院の強みや特色を活かした魅力的なコンテンツを作り出す余裕がないのが実情かと考えられます。
コンテンツの質が低下すると、フォロワーの離脱やエンゲージメント(いいね数やコメント数)の低下を招きます。
SNSマーケティングの成功には、医院の特色を活かした独自性のある情報発信が不可欠なのです。
投稿頻度の低下
SNSの投稿頻度が低下する原因は、主に3つの要因が挙げられます。
- SNS運用に十分な時間を確保できない
- 投稿ネタの枯渇
- SNS運用担当者の異動や退職により、運用ノウハウが途切れてしまう
投稿頻度を維持するためには、月間の投稿スケジュールを事前に組み、ネタのストックを確保することが有効です。
また、医院全体でSNS運用の重要性を共有し、スタッフ全員で情報収集する体制を整えましょう。
外部のSNSコンサルタントに運用を委託するのも、一つの解決策となるはずです。
外部へ動画制作を委託する際の注意点についてはこちらの記事で解説しています↓
動画制作を外注する際の注意点についてはこちら
https://unisent.co.jp/douga_marketing_sns_biyouclinic/

投稿頻度の低下は、フォロワーの離脱やエンゲージメント率の低下に直結する重要な問題点となります。
医院のSNS運用・コンテンツ制作ならユニセントにお任せ

クリニックのショート動画制作でお困りなら、ユニセントにお任せください。
クリニックの集患に繋がる動画をコスパ良く制作から運用まで支援いたします。
ユニセントでは、YouTubeを始めとするSNSに特化した動画制作支援を行っており、SNSアカウントコンセプトの作成、動画企画の作成、アルゴリズムに準拠した動画コンテンツ制作まで可能です。
ユニセントでは以下の特徴がございます
- 多ジャンルの複数YouTubeアカウントの運用パートナーとして企画コンサル・動画制作を担当
- YouTubeを始めとするSNS運用歴の長いコンサルタントが支援
- YouTube以外の関連施策もシームレスに提供可能
医院のSNSに関するお悩みをお抱えの方は、こちらから無料相談が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください↓
https://unisent.co.jp/contact/
今なら医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
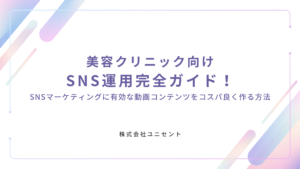
まとめ:医院のSNS運用・動画活用について
今回は、医療機関の集客方法に悩みを抱えている方に向けて、
- 医院がSNSを活用するメリットとデメリット
- 医院のSNSアカウント・動画コンテンツの活用方法
- SNSの種類と特徴
- 医院のSNS運用でよくある課題
上記について、医療機関のコンテンツ制作・マーケティングを支援してきた筆者の経験を交えながらお話してきました。
SNSを活用した集客は、今でも医院の成長に大きな可能性を秘めています。
むしろ、患者さんのオンライン情報収集が一般化した今こそ、取り組みどきと言えるでしょう。
これまでの従来型の集客方法に不安を感じていた方も、新しい一歩を踏み出すチャンスです。
医療機関としての信頼性を保ちながら、SNSという新しいツールを活用することで、より多くの患者さんとの出会いが生まれることでしょう。
地域医療に貢献したいという想いは、必ずSNSを通じて患者さんに届きます。
まずは小さな一歩から始めてみましょう。
SNSの特性を活かした情報発信で、あなたの医院の魅力を多くの方に伝えていけることを心から願っています。