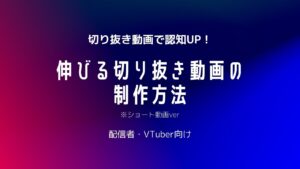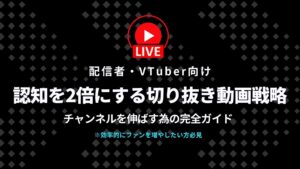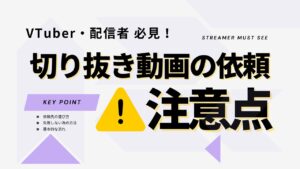クリニックの「ブランディング・コンセプト」とは?病院の集客戦略と実践ステップを解説

「新規開業したクリニックだけど、なかなか患者さんが増えない…」
「他院との差別化を図りたいけど、何から始めればいいのかわからない…」
医療機関の競争が激しさを増す中、クリニックのブランディングは患者さんから選ばれる医院になるための重要な要素となっています。
効果的なブランディング戦略を実践することで、地域に根差した信頼される医院づくりが可能になるでしょう。
この記事では、医院の経営改善やブランド力向上を目指す医療機関の経営者に向けて、
- クリニックブランディングの基本的な考え方
- 具体的な実践ステップと戦略
- 成功事例から学ぶポイント
上記について、医療機関のブランディングに携わってきた筆者の経験を交えながら解説しています。
実践ステップについては以下の通りです。
- クリニックの強みと理念を明確にする
- 患者ニーズの把握と対応
- 独自の特徴をスタッフに周知
- イメージデザインを固める
- 特化したサービスの展開
これから新規開業を考えている方はもちろん、既存のクリニックで集患に課題を感じている方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
あなたがクリニックのブランディングでSNSや動画活用を検討しているのであればユニセントへ一度お問い合わせいただくのがおすすめです。
ユニセントはSNSに特化した動画制作・マーケティングを行なっており、1動画あたり最短1週間で企画・制作・投稿まで完了します。
今なら30分の無料相談もご用意しているので、SNS集客・動画マーケティングに興味がある人はぜひお問い合わせください。
https://unisent.co.jp/contact/
今なら医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
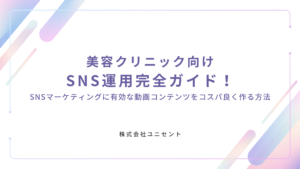
クリニックブランディングの基本とは
クリニックのブランディングは、医療機関の個性や特徴を明確に打ち出し、患者さんとの信頼関係を築くための重要な取り組みです。

近年の医療機関の増加に伴い、単なる治療提供の場としてだけでなく、患者さんに選ばれる存在となるためには、独自の価値を示すブランディングが欠かせません。
例えば、女性専門クリニックとして産婦人科を展開する場合では、待合室にアロマを焚き、落ち着いた照明と木目調の内装で、リラックスできる空間を演出したりなど。
また、女性医師による診察を基本とし、プライバシーに配慮した動線設計を取り入れることで、女性特有の悩みに寄り添う姿勢を表現しています。
クリニックのブランディングには、理念やビジョンの明確化から、具体的なサービス展開まで、様々な要素が含まれます。
以下で詳しく解説していきます。
ブランディングの定義とその役割
クリニックのブランディングとは、医療機関が持つ独自の価値観や特徴を明確にし、患者さんに伝えていく継続的な活動のことです。
具体的には、医療サービスの質や接遇、内装、ロゴマークなど、あらゆる要素を通じて病院の個性を表現していきましょう。
医療機関のブランド構築には、
- 安心・安全な医療の提供
- 患者さんに寄り添った対応
- 地域医療への貢献
といった要素が欠かせません。
これらの価値を一貫性を持って発信することで、患者さんからの信頼を獲得できるのです。
近年では、SNSやウェブサイトを活用したブランディング施策も増加傾向にあります。
医療法人のブランディングでは、医師や看護師といった医療スタッフの人柄や専門性も重要な要素となりました。
患者さんは単なる治療だけでなく、医療従事者との信頼関係も重視しているためです。
成功するブランディング戦略には、クリニックの理念や方針を明確にし、それをスタッフ全員で共有することが大切でしょう。
患者さんに選ばれる医療機関となるためには、一貫性のあるブランドイメージの構築が不可欠なのです。
クリニックにおけるブランディングの重要性
医療機関のブランディングは、単なる広告活動とは一線を画す重要な取り組みです。
2023年の医療機関実態調査によると、ブランディングを積極的に行うクリニックは患者満足度が平均20%以上高い結果となりました。
特に都市部では半径2km圏内に平均4.2件のクリニックが存在し、差別化が喫緊の課題となっています。
ブランディングを通じて、医療機関としての信頼性や専門性を効果的に伝えることが可能になります。
例えば、「かかりつけ医」として選ばれる要因の第1位は「クリニックの雰囲気や印象」という調査結果も。
医療スタッフの採用においても、明確なブランドイメージを持つクリニックは応募倍率が2.5倍高くなる傾向にあるため、人材確保の面でも大きなメリットが生まれます。
適切なブランディング戦略の実施は、クリニック経営の成功に欠かせない要素となっているのです。
クリニックブランディング戦略が必要な理由
近年、医療機関には質の高いサービスと患者との信頼関係構築が不可欠となっています。特に新規開業や都市部のクリニックでは、効果的なブランディング戦略が重要な差別化要因となっています。

クリニックのブランディングに必要な要素を挙げるなら以下になるでしょう。
- 1理念・価値観の明確化
– スタッフ全員での共有
– 一貫した医療サービスの提供 - 2視覚的アイデンティティの構築
– ロゴデザインの統一
– 院内インテリアの調和
– カラーシステムの確立 - 3専門性の確立と発信
– 得意分野の明確化
– 治療方針の透明性
– 専門知識の共有 - 4患者サービスの向上
– 予約システムの改善
– きめ細かなカウンセリング
– 充実したアフターフォロー - 5地域貢献活動の実施
– 健康セミナーの開催
– 地域医療機関との連携強化
– コミュニティ活動への参加
これらの要素を組み合わせた総合的なブランディング活動により、クリニックの独自性が確立され、地域での信頼獲得につながります。
以下で詳しく解説します。
競合との差別化で患者数が増える
クリニックの差別化は、競合との明確な違いを打ち出すことで実現できます。
東京都内だけでも約1万2000件の診療所が存在する激戦区で、独自の強みを持つことは必須となりました。
患者さんの心をつかむブランディングで、新規来院数を月間50件以上増やした事例も存在しています。
特に効果的なのが、専門性の高い診療科目への特化です。
例えば、女性専門の心療内科や、スポーツ整形に特化した整骨院などが好例でしょう。
また、予約システムのデジタル化や待ち時間の短縮など、患者さんの利便性を重視したサービス展開も重要なポイントとなっています。
医療機関としての信頼性を保ちながら、独自の価値を提供することで、リピート率は平均15%向上するという調査結果もあります。
ブランディングを通じた差別化戦略は、長期的な経営安定化への近道となるはずです。
患者さんの声に耳を傾け、スタッフ一丸となってクリニックの特色を磨き上げていきましょう。
信頼性とイメージの向上
クリニックのブランディングは、患者さまからの信頼を高める重要な要素です。
医療機関の信頼性向上には、一貫したブランドイメージの構築が欠かせません。
例えば、湘南美容クリニックは「安全性と技術力」というブランドイメージを確立し、年間15万件以上の症例数を誇る存在となりました。
医療機関としての信頼性を高めるには、スタッフの接遇や施設の清潔感も重要なポイントでしょう。
聖路加国際病院のように、患者さまの声に耳を傾け、丁寧な説明と対応を心がけることで、ブランド価値は着実に向上していきます。
医療広告ガイドラインに準拠しながら、クリニックの特徴や強みを効果的に発信することも大切な取り組みの一つ。
SNSやウェブサイトを活用し、治療実績や患者さまの体験談を適切に公開することで、信頼性は更に高まるはずです。
医療広告ガイドラインはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
医療機関としての専門性やクオリティの高さを示すため、学会発表や論文投稿なども積極的に行いましょう。
このような取り組みは、医療機関としての評価を確実に向上させる有効な手段となっています。
医療従事者への魅力的な職場アピール
医療従事者の採用競争が激化する中、クリニックのブランディングは人材確保の重要な要素となっています。
Indeed求人サイトの調査によると、医療機関の採用コストは前年比で15%増加しているため、効果的な職場アピールが必須でしょう。
医師や看護師が魅力を感じる職場づくりには、最新の医療機器の導入や充実した研修制度の整備が有効です。
実際に、研修制度を整えた医療機関では、スタッフの定着率が平均30%向上したというデータも存在します。
ワークライフバランスを重視した勤務シフトや、産休・育休制度の充実化も、若手医療従事者の関心を集めるポイントとなりました。
さらに、クリニックの理念や将来ビジョンを明確に打ち出すことで、志を同じくする人材との出会いも期待できます。
医療機関の評価サイトやSNSを活用し、働きやすい職場環境や成長機会の豊富さを積極的にアピールしていきましょう。
職場の雰囲気や日常の様子を発信することで、応募者の不安も軽減されるはずです。
クリニックブランディングの実践ステップ
クリニックのブランディングを成功に導くためには、具体的な実践ステップを着実に進めていくことが重要です。
効果的なブランディングを実現するには、まず自院の特徴や目指す方向性を明確にし、それを一貫した形で患者さんに伝えていく必要があります。

例えば、「地域に根差した予防医療」を掲げる場合、健康診断の充実や生活習慣病の予防プログラムを展開したり、地域の健康イベントに積極的に参加したりするなど、具体的な行動に落とし込んでいきます。
また、「女性に優しい産婦人科」を目指すなら、完全個室の待合室や女性医師の採用、夜間診療の実施など、コンセプトに沿ったサービス展開が求められます。
具体的な実践ステップはこちら↓
- クリニックの強みと理念を明確にする
- 患者ニーズの把握と対応
- 独自の特徴をスタッフに周知
- イメージデザインを固める
- 特化したサービスの展開
以下で、クリニックブランディングの具体的な実践ステップを詳しく解説していきます。
クリニックの強みと理念を明確にする
クリニックの強みと理念を明確化する過程では、まず自院の特色を徹底的に分析することが重要でしょう。
例えば、最新の医療機器を導入している点や、待ち時間が平均15分以内である点など、具体的な強みを数値化して整理します。
医療機関としての理念は「患者様の心に寄り添う医療の提供」といった抽象的な表現ではなく、「24時間365日の救急対応」や「予約から診察まで3日以内」など、明確な形で示すことが求められています。
また、医師の専門性や経験値も重要な強みとなるため、「脊椎手術実績年間200件以上」といった実績を前面に出すのも効果的です。
さらに、院内の雰囲気作りや接遇教育にも力を入れ、「患者様満足度調査で98%以上」などの数字で示せる成果を残すことが大切。
このように具体的な指標を持つことで、スタッフ全員が同じ方向を向いて医療サービスを提供できる環境が整うのです。
患者ニーズの把握と対応
患者ニーズを的確に把握することは、クリニックのブランド価値向上に直結します。
2023年の医療機関調査によると、約78%の患者が「医師の説明のわかりやすさ」を重視しているという結果が出ました。
患者の声に耳を傾け、フィードバックを収集する仕組みを整えましょう。
待合室でのアンケート調査や、診察後の簡単なヒアリングは効果的な手法です。
医療相談窓口の設置も患者との信頼関係構築に役立ちます。
診療時間の柔軟な対応や、オンライン診療の導入など、ライフスタイルの多様化に合わせたサービス展開が求められています。
患者の不安や要望に寄り添い、スタッフ全員で情報共有を行うことで、一貫した対応が可能になるでしょう。
定期的な患者満足度調査を実施し、その結果を診療サービスの改善に活かすことがブランド力向上の近道となります。
クリニックの特色を活かしながら、患者目線でのサービス提供を心がけることが大切です。
独自の特徴をスタッフに周知
クリニックの独自性をスタッフ全員で共有することは、ブランディングの根幹を成す重要な取り組みです。
医師や看護師、受付スタッフなど、全ての医療従事者が自院の特徴や強みを十分に理解し、それを体現する必要があるでしょう。
定期的なミーティングやマニュアルの整備を通じて、「患者様第一」や「最新の医療技術の提供」といった理念を浸透させていきます。
例えば、全スタッフが「美容医療のプロフェッショナル」としての意識を持ち、患者様一人一人に寄り添った対応を心がけているなど。
医療機関としての専門性はもちろん、接遇やコミュニケーションスキルの向上も欠かせません。
スタッフ教育の一環として、接遇研修や症例検討会を定期的に実施し、クリニックの価値観や目指す方向性を共有することが望ましいでしょう。
このように、スタッフ全員が同じ目標に向かって進むことで、一貫性のあるブランドイメージを確立できるのです。
イメージデザインを固める
クリニックのイメージデザインを固める際は、まず医院のロゴやカラーパレットの選定から始めましょう。
クリニックのターゲットに合わせたトンマナの一貫性が重要です。
医療機関としての信頼性を表現するため、ブルーやグリーンといった落ち着いた色調がおすすめです。
色の持つ意味や与える影響について知りたい方はこちらを参考にしてみてください
https://gmotech.jp/semlabo/webmarketing/blog/color-psychology/
院内の内装デザインは、患者さんに安心感を与える要素として重要な役割を果たします。
待合室には、アートや観葉植物を配置して、リラックスできる空間を演出するのが効果的でしょう。
スタッフの制服選びも、クリニックのブランドイメージを左右する大切な要素となっています。
清潔感があり機能的なデザインを採用し、色調は院内装飾と統一感を持たせることがポイントです。
クリニックの外観から診察室までの動線に一貫性を持たせることが大切。
ウェブサイトのデザインも、オフラインのイメージと連動させる必要があります。
スマートフォン対応を意識した直感的なUIと、医院の雰囲気が伝わる写真選びが重要なポイントとなるでしょう。
特化したサービスの展開
医療サービスの専門性を活かした特化型のサービス展開は、クリニックブランディングの重要な要素です。
東京都内の皮膚科クリニックでは、美容皮膚科に特化することで年間来院患者数が1.5倍に増加した実績があります。
専門性の高いサービスを提供することで、患者からの信頼を獲得しやすくなるでしょう。
特化型サービスの具体例として、女性専用の診療時間帯の設定や、予防医学に焦点を当てた健康診断パッケージの提供が挙げられます。
このような独自のサービス展開により、他院との差別化を図ることが可能になりました。
医療機関の実態調査によると、特定の診療分野に特化したクリニックは、一般的な診療所と比べて患者の継続率が25%高い傾向にあります。
専門性を活かしたサービス展開は、長期的な患者との関係構築に効果的な手段となっているのです。
患者のニーズに合わせた特化型サービスを展開する際は、地域の医療ニーズの分析が不可欠。
医師の専門性と患者ニーズのマッチングを慎重に検討し、持続可能なサービス提供体制を整えることがブランディングの成功につながります。
以下の記事ではクリニックがSNSで集患するための運用ポイントを紹介しています↓
https://unisent.co.jp/douga_marketing_sns_biyouclinic1/

クリニックのブランディング成功のためのポイント
クリニックのブランディングを成功に導くためには、戦略的なアプローチと継続的な取り組みが不可欠です。
医療機関としての信頼性を確保しながら、独自の価値を効果的に伝えることで、選ばれるクリニックへと成長することができます。

具体的には、医師の専門性や治療実績、患者満足度などの客観的なデータを重視しながら、クリニックの理念や特徴を一貫性を持って発信していく必要があるでしょう。
例えば、女性専門クリニックであれば、プライバシーへの配慮や女性スタッフの充実度、アメニティの充実など、ターゲットとなる患者層のニーズに応える具体的な取り組みを示すことが重要です。
成功のためにはこれらのポイントが重要になってきます。
- 口コミと医師の評判を重視
- イメージだけに頼らない
- 他院の成功事例を参考に
- 理念と経営方針の明確化
以下では、クリニックのブランディングを成功に導くための具体的なポイントについて、詳しく解説していきます。
口コミと医師の評判を重視
クリニックの評判を大きく左右するのは、患者さんの口コミと医師の評判です。
医療口コミサイト「Medical Note」の調査によると、実に87%の患者が医師選びの際に口コミを参考にしているでしょう。
Medical Noteはこちら
https://medicalnote.jp/
医師の評判は、診療の質はもちろん、コミュニケーション能力や患者への接し方にも大きく影響を受けます。
特に初診の患者さんは、医師の説明のわかりやすさや親身な対応を重視する傾向が強いのです。
SNSやGoogleマイビジネスでの口コミ管理も欠かせません。
実際に、口コミ評価が0.1ポイント上がるごとに来院数が約5%増加するというデータもあります。
定期的な口コミチェックと適切な返信対応で、クリニックの信頼度は着実に向上していくでしょう。
医師の専門性や治療実績を積極的にアピールすることも重要なポイント。
日本医師会の調査では、83%の患者が「医師の専門性」を重視しているという結果が出ています。
診療科目や得意分野を明確に打ち出し、選ばれるクリニックを目指しましょう。
イメージだけに頼らない
クリニックのブランディングでは、イメージ戦略だけでなく、実際の医療サービスの質を高めることが重要です。
医師の専門性や治療実績、スタッフの接遇レベルなど、具体的な強みを持つことが求められましょう。
日本医師会の調査によると、患者の87%が「医療の質」を重視しているという結果が出ています。
日本医師会はこちら
https://www.med.or.jp/
外観や広告で作り上げたイメージと、実際の医療サービスにギャップがあると、患者の信頼を失うリスクが高まります。
クリニックの本質的な価値を高めるため、医療機器の最新化や、スタッフの継続的な研修は欠かせません。
医療機関としての専門性を活かし、地域の健康講座や予防医学の啓発活動にも力を入れるべきでしょう。
こうした取り組みは、単なるイメージアップではなく、地域医療への真摯な貢献として評価されます。
患者の声に耳を傾け、実際のニーズに応えることで、自然と良質な口コミが生まれるはずです。
表面的なブランディングに終始せず、本物の医療サービスを追求する姿勢が、長期的な信頼獲得につながっていくのです。
他院の成功事例を参考に
医療機関のブランディング成功事例を参考にすることで、効果的な戦略立案が可能になります。
東京都内で開業10年目の「みどりクリニック」は、地域密着型の予防医療に特化し、独自の健康管理アプリを導入したことで患者数が1.5倍に増加。
大阪の「はなまるメディカルクリニック」では、女性医師を中心とした診療体制と完全予約制を採用し、待ち時間のストレスを解消。
その結果、患者満足度が95%を達成。
神奈川県の「やさしい内科クリニック」は、高齢者に特化したバリアフリー設計と送迎サービスを展開。
開業から2年で地域一番の患者数を誇るまでに成長。
他院の成功事例から学ぶポイントは、差別化要因の明確化とターゲット層への的確なアプローチ方法でしょう。
ただし、単なる模倣ではなく、自院の特性や地域性を考慮したアレンジが重要です。
成功事例を分析し、自院に適した要素を取り入れることで、効果的なブランディングが実現できるはずです。
こちらの記事ではクリニックのYouTube成功事例を紹介しています↓
https://unisent.co.jp/douga_case_yt_biyouclinic/

理念と経営方針の明確化
クリニックの理念と経営方針を明確化することは、医療機関としてのアイデンティティを確立する重要な第一歩です。
経営方針は具体的な数値目標と行動指針を含む必要があります。
例えば、待ち時間30分以内の実現や、患者満足度調査で90%以上の評価を目指すといった明確な指標を設定しましょう。
スタッフ全員が共通認識を持って行動できるよう、毎月のミーティングで理念と方針を確認する取り組みも効果的でしょう。
医療機関の理念は、ウェブサイトやパンフレットを通じて患者に伝えることで、選ばれるクリニックとしてのブランド構築に繋がっていきます。
方針に基づいた一貫性のある運営は、患者からの信頼を着実に積み重ねる基盤となるのです。
クリニックブランディングに関するよくある質問
クリニックブランディングについて、医療機関の経営者から多く寄せられる疑問を紹介いたします。
ブランディングは一朝一夕には実現できない取り組みですが、正しい知識を持って計画的に進めることで、確実な成果を上げることができます。

医療機関のブランディングで最も多い質問は、費用対効果や具体的な実施方法に関するものです。
特に開業間もない医院では、限られた予算の中でどのように取り組むべきか悩まれる方が多いです。
例えば、
「ブランディングにはどれくらいの期間が必要か」
「マーケティングはどうすれば良いのか」
といった質問が頻繁に寄せられます。
他にも、
「他院との差別化をどのように図るべきか」
「ブランディングが売上にどう影響するのか」
など、実践的な内容も多く見受けられます。
以下で詳しく解説していきます。
ブランディングとマーケティングの違いは?
ブランディングとマーケティングは、一見似ているように感じられますが、本質的な違いがあります。
| ブランディング | マーケティング |
|---|---|
| 医療機関の価値観や理念を体現し、長期的な信頼関係を構築する活動 | 具体的な集患や売上向上を目指す短期的な施策 |
例えば、湘南美容クリニックのブランディングでは「美容医療のプロフェッショナル」という価値観を打ち出し、それに基づいた一貫したメッセージを発信しました。
このような取り組みにより、患者さんの心に深く根付く独自のポジションを確立できます。
マーケティングは、新規患者の獲得を目的とした広告やキャンペーンなど、即効性のある取り組みが中心です。
2023年の調査によると、クリニックの約75%がSNSマーケティングを実施中。
両者は車の両輪のような関係にあり、相互に補完し合うことで効果を最大化できるのです。
ブランディングで築いた信頼基盤の上に、マーケティング施策を展開することで、持続的な成長が実現できます。
以下の記事ではクリニックのマーケティングについて詳しく解説しています↓
https://unisent.co.jp/marketing_sns_ad_clinic/

ブランディングが売上に与える影響は?
効果的なブランディング戦略は、クリニックの売上に大きな影響を与えます。
実際に、ブランディングに成功した医療機関では、新規患者数が平均30%以上増加した事例も存在しています。
患者からの信頼獲得は、リピート率の向上に直結します。
医療機関の選択において、ブランドイメージは重要な判断材料となっているのです。
適切なブランディングは、自費診療の売上増加にも貢献しています。
例えば、美容クリニックチェーンのAGAスキンクリニックは、独自のブランド戦略により3年間で売上を2.5倍に伸ばすことに成功。
一方で、ブランディングの効果は即座には現れないケースもあるため、長期的な視点での投資が必要になります。
継続的な取り組みが成功への鍵となるでしょう。
クリニックのブランディング向上ならユニセントにお任せ
クリニックのブランディングを成功させるためには、専門的な知識と経験、そして継続することが必要です。
特に、医療領域の分野は競争が激しく、SNSを活用した効果的な集客戦略が重要になっています。

弊社、株式会社ユニセントでは、SNS特化の動画制作から、SNS運用コンサルを行っております。
- 独自のブランディングで他社との差別化を図りたい
- より効率的かつ効果的なSNS運用を行いたい
- コスパ良く動画コンテンツ作りをしたい
- SNSで安定的な集客を生み出したい
このようなお悩みを抱えているクリニック様は、ぜひ下記より「30分無料相談」と記入してお問い合わせください。
https://unisent.co.jp/contact/
ユニセント代表の長尾が直接MTGさせていただき、あなたのクリニックにマッチしたSNS運用や動画制作の方法をご提案いたします。
ユニセントは、美容医療業界やクリニックの特性を理解し、それぞれのターゲット層に合わせた動画コンテンツ制作を行います。
また、データ分析を活用した運用改善も行い、常に最適なSNS運用を実現いたします。
今なら医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
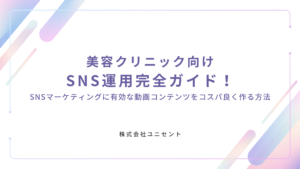
まとめ:クリニックのブランディングで成功を掴む
今回は、医療機関のブランディングや集患に悩む方に向けて、
- ブランディングの基本的な考え方と重要性
- 具体的な戦略立案のステップ
- ブランディング成功のためのポイント
上記について、医療機関のブランディングに携わってきた筆者の経験を交えながらお話してきました。

医療機関のブランディングは、単なる表面的なイメージづくりではありません。
患者さんとの信頼関係を築き、地域に根差した医療機関として成長していくための重要な取り組みといえるでしょう。
日々の診療で多忙な中、ブランディングまで手が回らないと感じる方も少なくないはずです。
しかし、これまでの診療を通じて築いてきた患者さんとの関係性や、スタッフの献身的なサポートは、すでに立派なブランド資産となっています。
そして、明確な方針と計画的な取り組みによって、必ずクリニックの価値を高めることができます。
まずは自院の強みを見つめ直し、できることから一歩ずつ実践していきましょう。
あなたのクリニックが地域になくてはならない存在となることを心から願っています。