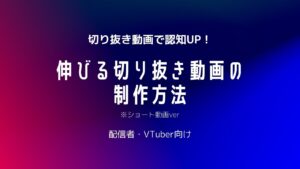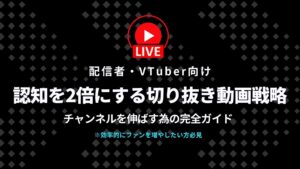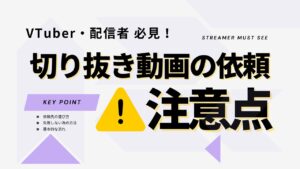集客の参考に!病院の「SNS活用事例」と「運用方法」を徹底解説

最近、病院の経営や広報活動においてSNSを活用することが重要視されていますが、
「どのようにSNSを活用すれば効果的なのか…」
「成功事例を参考にしたいけれど、どこから始めればいいのか…」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
SNSはうまく活用することで、病院の集客力やブランディングを高めることが可能です。
実際の成功事例や具体的な運用方法を知ることで、あなたの病院でもSNSを効果的に取り入れることができるでしょう。
この記事では、病院の経営者や広報担当者の方に向けて、
- SNS活用の成功事例
- 効果的な運用方法
- 病院のSNS活用でよくある失敗例
上記について、解説しています。
病院のSNS活用は、初めての方でも少しの工夫で大きな成果を得ることができる分野です。
成功事例からあなたの病院に最適なSNS活用法のヒントを見つけてみてください。
もしあなたがSNSを活用し、集客したいとを考えているのであれば、ユニセントへ一度お問い合わせいただくのがおすすめです。
今なら無料であなたのクリニックに最適なSNS運用の戦略プランをご提案いたします。
https://unisent.co.jp/contact/
ユニセントはSNSに特化した動画制作・マーケティングを行なっており、1動画あたり最短1週間で企画・制作・投稿まで完了します。
SNS集客・動画マーケティングに興味がある人はぜひお問い合わせください。
今なら医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
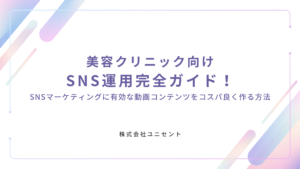
病院が活用できるSNS一覧と各媒体の特徴
病院がSNSを活用する際には、各SNSプラットフォームの特徴を理解し、それぞれの強みを最大限に活用することが重要です。

各SNSプラットフォームの一覧と特徴は以下の通りです
| SNSプラットフォーム | 特徴 | 活用方法 |
|---|---|---|
| LINE公式アカウント | 患者との直接的なコミュニケーションが可能 | 予約や問い合わせの対応 |
| YouTube | 動画を通じて診療内容や医師を紹介 | 患者の信頼獲得 |
| 視覚的なコンテンツが強み | 病院の雰囲気やスタッフ紹介 | |
| 情報量が多い | イベントやキャンペーンの告知 | |
| TikTok | 短い動画で魅力を伝える | 若年層へのアプローチ |
| X(旧Twitter) | リアルタイム情報発信が得意 | 緊急のお知らせや最新情報の共有 |
各SNSの特性を活かし、病院のブランディングや患者との関係構築を進めることが可能です。
これにより、病院の知名度向上や患者の増加が期待できます。
以下で各SNSについて詳しく解説します。
LINE公式アカウント
LINE公式アカウントは、病院が患者とのコミュニケーションを円滑に進めるための有効なツールです。
LINE公式アカウントを利用することで、患者への情報発信が簡単になり、予約の確認やキャンセル、健康情報の提供などがスムーズに行えます。
特に、LINEは多くの人が日常的に使用しており、通知が即座に届くため、患者との接点を強化する手段として非常に有効です。
LINE公式アカウントを活用する理由は、まずコスト効率の良さです。
従来の紙媒体や電話による連絡と比べ、LINEを使った情報発信はコストが抑えられます。
また、患者が自分のタイミングでメッセージを確認できるため、相手に負担をかけずに情報を届けることが可能です。
「忙しい患者さんが多いかもしれない…」と感じる方には、LINEの利便性が大きな助けとなるでしょう。
さらに、LINE公式アカウントを活用することで、患者からのフィードバックをリアルタイムで受け取ることができ、サービスの改善にも役立ちます。
LINE公式アカウントは、病院が患者とのコミュニケーションを強化し、サービス向上に繋がる重要なツールです。
YouTube(ユーチューブ)
YouTubeは病院がSNSを活用する上で非常に効果的なプラットフォームです。
動画を通じて、病院の設備や医師の紹介、治療法の説明などを視覚的に伝えることができます。
特に、手術の流れや医療機器の使い方を動画で示すことで、患者の不安を和らげる効果があります。
「どんな治療を受けるのか不安…」と感じている方にとって、視覚的な情報は安心感を与えるでしょう。
また、YouTubeは検索エンジンとしても機能しており、適切なキーワードを設定することで、病院の動画が長期的に多くの人に見られる可能性が高まります。
さらに、動画のコメント欄を通じて患者と直接コミュニケーションを取ることもでき、信頼関係の構築に役立ちます。
YouTubeを活用することで、病院の専門性をアピールしつつ、患者との距離を縮めることが可能です。
Instagram(インスタグラム)
Instagram(インスタグラム)は、視覚的なコンテンツを中心に、病院がその魅力を効果的に伝えるためのプラットフォームとして非常に有効です。
特に、日々の診療風景や施設内の様子を写真や短い動画で共有することで、患者に親しみを持ってもらうことができます。
また、インスタグラムのストーリーズ機能を活用すれば、24時間限定の情報を発信することができ、緊急のお知らせやキャンペーン情報をタイムリーに届けることが可能です。
「病院の雰囲気を知りたい…」と考える患者にとって、インスタグラムはリアルな情報源となります。
さらに、ハッシュタグを活用することで、特定の医療分野や地域に関心のあるユーザーに情報を届けることができます。
これにより、ターゲット層へのリーチが広がり、集客効果が期待できます。
インスタグラムを通じて、ビジュアルを重視した情報発信が可能となり、病院の魅力を最大限に引き出すことができます。
Facebook(フェイスブック)
Facebook(フェイスブック)は、病院がSNSを活用する際に非常に有効なプラットフォームです。
理由は幅広い年齢層に対して情報を届けることができるからです。
特に、40代以上の利用者が多く、家族連れや中高年層をターゲットにした情報発信が可能です。
例えば、健康セミナーの案内や予防接種の情報を投稿することで、地域の住民に対して直接的なアプローチができます。
また、Facebookの「いいね!」や「シェア」機能を活用することで、投稿が拡散されやすくなり、自然と病院の知名度が向上します。
さらに、コメント機能を使って患者とのコミュニケーションを図ることも可能です。
これにより、患者の疑問や不安に迅速に対応できるため、信頼関係の構築に役立ちます。
ただし、投稿内容は慎重に選ぶ必要があります。
医療情報の発信においては、正確性と信頼性が求められるため、専門家による監修を受けることが重要です。
Facebookを通じて、病院の存在感を高め、地域社会との結びつきを強化することができます。
TikTok(ティックトック)
TikTokは、病院がSNSを活用する際に注目すべきプラットフォームの一つです。
短い動画で視覚的に訴求できるため、医療情報を分かりやすく伝えるのに適しています。
ある病院では医師や看護師が健康に関する豆知識を短い動画で紹介し、視聴者の関心を引いています。
「病院の情報発信は堅苦しいかもしれない…」と感じる方もいるでしょうが、TikTokのカジュアルな雰囲気を活かせば、親しみやすい印象を与えることが可能です。
また、ハッシュタグを活用することで、特定のテーマに興味を持つユーザーにリーチしやすくなります。
運用のポイントとしては、動画のクオリティを保ちつつ、視聴者が楽しめるコンテンツを定期的に更新することが重要です。
TikTokの活用により、病院は新しい層の患者にアプローチし、認知度を高めることができます。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は、病院がSNSを活用する際に有効なプラットフォームの一つです。
Xは即時性のある情報発信と患者との双方向コミュニケーションを可能にします。
これにより、病院は最新の医療情報やイベント告知を迅速に発信でき、フォロワーからの質問やフィードバックに素早く対応することができます。
Xの特徴は短文での情報発信が可能であり、リアルタイムでの情報共有がしやすい点にあります。
このため、医療機関が時事的なトピックや緊急の情報を発信するのに適しています。
また、ハッシュタグを利用することで、特定のテーマに興味を持つユーザーに情報を届けやすくなります。
例えば、インフルエンザの流行時期には「#インフルエンザ予防」などのハッシュタグを用いることで、関連情報を求める多くのユーザーにリーチできます。
「SNSの運用は難しいかもしれない…」と感じる方もいるでしょうが、Xの特性を理解し活用することで、効果的な情報発信が可能です。
要点として、Xは病院にとって即応性と幅広い情報拡散力を持つ重要なSNSツールです。
以下の記事では0から始める医療業界のSEO対策・広告戦略をテーマに解説しています。

病院がSNSを活用するメリット
病院がSNSを活用することで、さまざまな利点があります。
以下にその主なポイントをまとめます。
- コスト効率の良い情報発信
- 広告費を削減し、ターゲット層に直接アプローチ
- 効率的な情報発信が可能
- 患者数の増加
- 若年層やデジタルネイティブ世代に効果的にアピール
- 病院の存在やサービスを広く認知させる
- 即時性のある情報伝達
- 緊急のお知らせやキャンペーン情報をタイムリーに発信。
- 患者とのスムーズなコミュニケーションを促進。
- ブランドイメージの向上
- 定期的な情報発信で信頼性や親しみやすさをアピール。
- Instagramなどで院内の雰囲気やスタッフを紹介し、安心感を提供。

SNSの活用は、病院経営において重要な役割を果たします。
効果的な運用により、患者との信頼関係を築き、病院のブランド力を高めることが可能です。
以下で詳しく解説します。
コストを抑えた情報発信が可能
病院がSNSを活用する最大のメリットの一つは、コストを抑えた情報発信が可能である点です。
従来の広告手法、例えばテレビや新聞広告は、莫大な費用がかかることが一般的です。
しかし、SNSを利用することで、比較的低コストで、しかも広範囲に情報を届けることができます。
例えば、FacebookやInstagramでは、無料でアカウントを開設し、情報を発信することが可能です。
さらに、特定のターゲット層に向けた広告を出稿する場合でも、予算に応じた柔軟な設定が可能です。
このように、低コストでありながら効果的な情報発信ができるため、予算に限りがある病院でも容易に取り組むことができます。
「予算の制約で広告を諦めていた…」という方も、SNSなら新たな可能性を見出せるかもしれません。
SNSを活用することで、病院は効率的に情報を広めることができ、結果として集客や患者数の増加につながることが期待されます。
患者数の増加に貢献
患者数の増加に貢献するために、病院がSNSを活用することは非常に効果的です。
SNSを通じて、病院の存在や特色を広く知ってもらうことができ、潜在的な患者にアプローチするチャンスが増えます。
特に、医療機関の専門性や最新の医療技術、スタッフの紹介などを発信することで、患者の信頼を得ることができます。
「SNSを使っても本当に患者が増えるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
しかし、具体的な事例として、ある病院ではInstagramを活用して健康情報や医師のインタビューを定期的に配信した結果、来院者数が増加した例もあります。
SNSでの情報発信は、地域を超えて広がるため、遠方からの新規患者を引き寄せることも可能です。
結果として、病院の知名度向上や、患者の増加につながるのです。
SNSを通じた情報発信は、病院の認知度を高め、患者数の増加に大いに貢献します。
即時性のある情報伝達
即時性のある情報伝達は、病院がSNSを活用する大きなメリットです。
特に緊急な情報や季節ごとの予防接種の案内など、素早く患者に伝えたい情報をタイムリーに発信できます。
たとえば、インフルエンザの流行や新型コロナウイルスの感染状況に関する最新情報を、SNSを通じてリアルタイムで共有することで、患者の不安を和らげることができます。
「急な休診のお知らせをどうやって患者に伝えよう…」と悩むこともあるでしょうが、SNSならその心配も解消されます。
また、患者からの問い合わせや予約の変更など、即時対応が求められるコミュニケーションにも対応可能です。
こうした即時性のある情報伝達は、患者との信頼関係を築く上でも非常に重要です。
即時性を活用することで、病院は患者に対し迅速で信頼性の高い情報を提供できます。
患者とのコミュニケーション促進
患者とのコミュニケーションを促進するために、SNSは非常に有効な手段です。
病院がSNSを活用することで、患者との距離を縮め、信頼関係を築くことが可能になります。
例えば、LINE公式アカウントを通じて、診療時間や休診日などの情報を手軽に発信することができます。
これにより、患者は必要な情報を迅速に得ることができ、「病院に行く前に確認できて安心だ」と感じるでしょう。
また、InstagramやFacebookを利用して、病院内の様子や医師の紹介などをビジュアルで伝えることも効果的です。
これにより、病院の雰囲気を事前に知ることができ、「初めての病院でも安心して行けるかもしれない…」と感じる患者も増えるでしょう。
さらに、SNS上で患者からの質問に迅速に対応することで、患者の不安を解消し、信頼を深めることができます。
SNSを活用することで、患者とのコミュニケーションを円滑にし、信頼関係を築くことが可能です。
以下の記事では今から動画やSNSは遅い?失敗しないSNS活用と動画制作というテーマについて解説しています。

ブランドイメージの向上(ブランディング)
病院がSNSを活用することで、ブランドイメージの向上が期待できます。
特に「病院のイメージをもっと良くしたい…」と考えている方には、SNSを通じたブランディングが効果的です。
SNSを通じて、病院の特徴や強みを視覚的に伝えられるため、患者や地域住民に対する信頼感が高まります。
例えば、院内の清潔さや最新の医療設備、スタッフの専門性を動画や写真で紹介することで、親しみやすさや安心感を提供できます。
また、患者からの好意的なコメントやレビューが集まることで、他の人々の信頼を得る助けになります。
ただし、情報発信は一貫性を持たせ、誤解を招かないように注意が必要です。
こうした取り組みによって、病院のブランドイメージを効果的に向上させることが可能です。
以下の記事では医療業界のブランディング実践ステップをテーマにしています。

病院がSNSを活用する際のデメリット
病院がSNSを利用する際には、デメリットを理解しつつ、適切な戦略を立てることが重要です。
以下は、病院のSNS活用におけるデメリットとなる点です。
- 運用に時間と労力が必要
- 効果が現れるまで時間がかかる
- 失敗時の評判リスク
これらのポイントを押さえ、SNS運用をぜひ成功させましょう。
以下で各デメリットについて詳しく解説します。

運用に時間と労力が必要
運用に時間と労力が必要という点は、病院がSNSを活用する際の大きなデメリットです。
SNSは常に新しい情報を求められるため、定期的な更新が不可欠です。
これには、コンテンツの企画、制作、投稿、分析、そしてフォロワーとのやり取りといった多岐にわたる作業が含まれます。
「忙しい日々の中で、こんなに手間がかかるのは大変かもしれない…」と感じる方もいるでしょう。
しかし、これらの作業を効率的に行うためには、専門のスタッフを配置するか、外部のプロフェッショナルに委託することが有効です。
さらに、SNS運用のスケジュールを事前に立てておくことで、日々の負担を軽減することができます。
最終的には、計画的な運用が成功への鍵となるでしょう。
効果が現れるまで時間がかかる
効果が現れるまで時間がかかる理由は、SNS運用には継続的な努力が必要だからです。
病院がSNSを活用する際、即座に結果を求めてしまうと、期待通りの効果が得られないことがあります。
SNSは、フォロワーの増加やエンゲージメントの向上に時間を要するため、短期間での劇的な変化を期待するのは難しいでしょう。
特に、新たにアカウントを開設した場合、最初はフォロワー数が少なく、投稿のリーチも限定的です。
そのため、定期的な投稿やフォロワーとのコミュニケーションを通じて、徐々に信頼関係を築いていくことが重要です。
また、SNSのアルゴリズムは頻繁に変化するため、常に最新のトレンドや効果的な運用方法を学び続ける必要があります。
「結果が出なくて焦るかもしれない…」と感じる方もいるでしょうが、忍耐強く取り組むことで、徐々に効果が見えてくるはずです。
SNS運用は長期的な視点で取り組むことが成功への鍵です。
失敗時の評判リスク
失敗時の評判リスクは、病院がSNSを活用する際に注意すべき重要なポイントです。
SNSは情報が瞬時に広がるため、誤った情報や不適切な発言が拡散されると、病院の評判に大きなダメージを与える可能性があります。
たとえば、患者情報の漏洩や誤った医療情報の発信は、信頼を失うだけでなく法的な問題にも発展する恐れがあります。
「SNSを活用してみたいけど、失敗したらどうしよう…」と不安に思う方もいるでしょう。
こうしたリスクを軽減するためには、投稿内容の事前チェックや、情報発信のガイドラインを設けることが重要です。
また、SNS運用チーム内でのコミュニケーションを密にし、迅速に対応できる体制を整えることも必要です。
これにより、リスクを最小限に抑えつつ、効果的なSNS活用を実現できます。
評判リスクを管理するためには、事前の準備と体制整備が欠かせません。
SNS活用の成功事例紹介
病院がSNSを活用することで、患者とのコミュニケーションを強化し、信頼を築くことができます。
以下に具体的な事例を示します。
- YouTubeでの情報発信
- 専門医による健康情報の動画配信
- 患者が自宅で専門的な健康情報を視聴でき、安心感を得られる
- タイムリーな情報提供
- 新しい治療法や健康情報を迅速に発信
- 専門医による健康情報の動画配信
- Instagramでの親しみやすさの向上
- 病院の日常やスタッフの紹介
- 親しみやすいイメージを発信し、患者との距離を縮める
- ビジュアルコンテンツの活用
- 写真や短い動画で、病院の雰囲気を伝える
- 病院の日常やスタッフの紹介
- TikTokでの楽しい健康教育
- 短い動画で健康知識を伝える
- 楽しく学べるコンテンツで、若い世代にもアプローチ
- トレンドを活用した情報発信
- 流行を取り入れたコンテンツで、視聴者の興味を引く
- 短い動画で健康知識を伝える
- SNS運用方法のポイント
- ターゲットの明確化
- 患者層や地域に合わせたコンテンツを作成
- コンテンツの一貫性
- 統一されたメッセージとデザインで信頼感を醸成
- フィードバックの活用
- 患者からのコメントや反応を元に、コンテンツを改善
- ターゲットの明確化
これらの方法を活用することで、病院はSNSを通じて患者との関係を深め、地域社会への貢献を強化できます。
以下で病院のSNS活用の成功事例を紹介します。

YouTubeを活用した事例
友利新公式チャンネルは内科・皮膚科医の友利新先生が運営し、美容や健康、スキンケアなど多角的なテーマを扱っています。
ニキビケアやダイエット、マスク生活の肌トラブル解決法が多く、専門的かつ実践的なアドバイスで視聴者の悩みに寄り添った動画が人気です。
専門知識をわかりやすく解説する信頼性と親しみやすさを同時に打ち出し、サムネイルやタイトルで具体的な悩みをダイレクトに提示することで検索流入も獲得されています。
以下の記事では医療業界のYouTube運用の活用事例をより詳しく紹介しています。

Instagramを活用した事例
自由が丘クリニックソフィア|形成外科・美容外科・美容皮膚科
https://www.instagram.com/clinicsophia/
こちらのクリニックのInstagramでは、施術紹介やQ&A、YouTubeの切り抜きを紹介する動画が人気です。
特に肌治療系で悩み別のケア方法を短いリールでわかりやすく発信されています。
また、専門医師が登場することで信頼感を醸成し、フォローを促すキャンペーンやQ&A企画などでユーザーとのコミュニケーションを積極的に図っています。
以下の記事では医療業界のインスタグラム運用の活用事例をより詳しく紹介しています。

TikTokを活用した事例
dr.harada.hiromitsu 二重整形/埋没法 原田浩光
二重整形/埋没法 原田浩光医師のTikTokでは、施術のビフォーアフターや、実際にカウンセリングを受ける流れを紹介する動画が人気を集めています。
短いクリップで施術のプロセスをわかりやすく示し、施術後の仕上がりを強調する構成が特徴的です。
さらにコメント欄でのQ&Aや、専門的な情報を挟むことでユーザーの信頼を獲得し、フォロワー数を着実に伸ばしています。
以下の記事では医療業界のTikTok運用の活用事例をより詳しく紹介しています。

病院が安全にSNSで集客をするための運用ポイント
病院がSNSを安全かつ効果的に活用するためには、いくつかの重要な運用ポイントを押さえる必要があります。
以下に、SNS運用ポイントをまとめましたので、参考にしてみてください。
医療業界特有の規制と患者プライバシーの考慮
- 医療広告ガイドラインの遵守
- 法令違反を防ぐために、医療広告ガイドラインに従った情報発信を行います
- 信頼性が高まり、患者からの信頼も得られます
- 法令違反を防ぐために、医療広告ガイドラインに従った情報発信を行います
- 患者プライバシーの保護
- 患者の個人情報を守るために、プライバシーに配慮した投稿内容を心掛けます
- 具体的な患者情報を含まない形での情報発信が求められます
- 患者の個人情報を守るために、プライバシーに配慮した投稿内容を心掛けます
効果的な情報発信とコミュニケーションの強化
- 投稿者の選定と管理
- SNSの投稿者を適切に選定し、管理することで、情報の一貫性と信頼性を確保
- 医療知識を持つスタッフが関与することが望ましい
- SNSの投稿者を適切に選定し、管理することで、情報の一貫性と信頼性を確保
- ネットリテラシー教育の実施
- スタッフに対してネットリテラシー教育を行い、適切なSNS運用スキルを身につける
- 誤った情報発信を防ぐ
- スタッフに対してネットリテラシー教育を行い、適切なSNS運用スキルを身につける
これらのポイントを押さえることで、病院はSNSを通じて安全かつ効果的に情報を発信し、集客やブランドイメージの向上に繋げることができます。
以下で各項目について詳しく解説します。

医療広告ガイドライン作成の重要性
医療広告ガイドライン作成の重要性は、病院がSNSを活用する際に非常に重要です。
まず、医療広告には法律で定められた規制があり、これを遵守しないと罰則を受ける可能性があります。
特に、SNSは不特定多数に情報を発信するため、誤解を招く表現や過度な宣伝は避けるべきです。
「SNSでの情報発信は簡単かもしれない…」と思う方もいるでしょうが、医療情報の信頼性を確保することが最優先です。
ガイドラインを作成することで、どのような情報をどのように伝えるべきかが明確になり、スタッフ全員が一貫した方針で運用できます。
これにより、病院の信頼性を保ちつつ、患者との信頼関係を築くことが可能です。
要するに、医療広告ガイドラインは、SNS運用の基盤を固め、病院の信頼性を守るための重要な手段です。
医療広告ガイドラインはこちらをご確認ください↓
投稿者の選定と管理
投稿者の選定と管理は、病院がSNSを活用する際に非常に重要なポイントです。
適切な投稿者を選ぶことで、情報の信頼性や発信力が大きく向上します。
まず、医療に関する専門知識を持つスタッフを投稿者に選定することが求められます。
これにより、正確で信頼性の高い情報を発信できるでしょう。
また、投稿者の管理も重要です。
定期的にSNS運用の方針を確認し、投稿内容のチェックを行うことで、誤った情報の発信を防ぎます。
「SNS運用って難しそう…」と感じる方もいるかもしれませんが、管理体制を整えることでリスクを最小限に抑えることが可能です。
さらに、投稿者にはネットリテラシー教育を行い、SNSの特性やリスクについて十分に理解させることが必要です。
これにより、トラブルを未然に防ぎ、病院のブランドイメージを守ることができます。
要するに、投稿者の選定と管理は、病院のSNS活用において成功の鍵を握る要素です。
ネットリテラシー教育の実施
ネットリテラシー教育の実施は、病院がSNSを安全かつ効果的に活用するために不可欠です。
ネットリテラシーとは、オンライン上での情報の取り扱いやコミュニケーションの方法についての理解を指します。
医療機関においては、患者の個人情報を守る責任があり、誤った情報発信は信頼を損なうリスクがあるため、スタッフ全員がネットリテラシーを高めることが重要です。
具体的には、SNS上での個人情報の扱い方や、誤解を招かない表現方法についての研修を行うことが考えられます。
「SNSで何を発信するべきか、何を避けるべきか…」と悩む方もいるでしょう。
そこで、実際の事例を交えた教育プログラムを導入することが効果的です。
また、定期的な勉強会を開催し、最新のSNSトレンドやガイドラインについての情報を共有することも大切です。
このような取り組みにより、病院のSNS運用がより安全で効果的になり、患者との信頼関係の構築にもつながります。
以下の記事では医療業界のマーケティング施策の実践ステップと失敗事例について解説しています。

最適なコンテンツ制作(動画や画像など)
最適なコンテンツ制作は、病院がSNSで成功するために重要な要素です。
まず、視覚的に魅力的な画像や動画を作成することが重要です。
例えば、診療科ごとの紹介動画や、医師やスタッフのインタビューを通じて、病院の雰囲気や専門性を伝えることができます。
「自分の病院の魅力をどう伝えたらいいのだろう…」と悩む方もいるでしょうが、患者目線での情報提供を心がけると良いでしょう。
次に、コンテンツは一貫性を持たせることが大切です。
定期的な投稿や、テーマに沿った内容を提供することで、フォロワーの信頼を得られます。
また、患者の声や体験談を取り入れると、信頼性が増します。
これにより、病院の人間味や親しみやすさを感じてもらうことができるでしょう。
最適なコンテンツ制作は、病院の専門性と親しみやすさを効果的に伝える手段となります。
自院で最適なコンテンツを制作することが困難な場合は、外部の専門業者に依頼するのも一つの手です。
SNS運用の知識が何もない場合は特に有効なアドバイスを受けられることができます。
弊社、ユニセントではSNSの企画・動画制作・運用・分析まで一貫して支援させていただいております。
SNS運用に関してお困りの方は「無料相談の依頼」とお問い合わせください。
https://unisent.co.jp/contact/
まずはあなたにあったSNSの戦略プランを無料でご提案いたします。
以下の記事では医療業界向けに「ショート動画で集客に繋げる」活用方法について解説しています。

病院のSNS活用でよくある失敗例
病院がSNSを活用する際によくある失敗として、以下のような例が挙げられます。
- クオリティの低いコンテンツの量産
- 正しく分析・改善が行えていない
- ターゲットに求められていないコンテンツの発信

初めてSNS運用に挑戦する方によくある失敗あるあるとして、インプレッションや再生回数にばかり気を取られ、本当に価値ある情報を届けられていない、なんて事が多いです。
見かけだけの再生数や登録者が伸びても集客に繋がらない、なんてことはよくあります。
このような失敗を避けるためのポイントを以下で詳しく解説していきます。
クオリティの低いコンテンツの量産
クオリティの低いコンテンツの量産は、病院のSNS活用において大きな失敗につながる可能性があります。
SNSは情報の拡散力が高く、魅力的なコンテンツであれば多くの人に届きますが、逆に質の低いものはフォロワーを失う原因となりかねません。
「どうせ見てもらえないかもしれない…」と手を抜いてしまうと、結果的に病院の印象を悪化させてしまいます。
多くの病院は、投稿の頻度を重視するあまり、内容の質を犠牲にすることがあります。
これは、フォロワーの信頼を失い、最終的には患者数の減少につながるリスクがあります。
この問題を解決するためには、まずコンテンツの質を最優先に考えることが重要です。
具体的には、情報の正確性や視覚的な魅力を高めることが求められます。
また、投稿前に必ず内容をチェックし、医療の専門家による監修を受けることで、信頼性の高い情報発信を心がけましょう。
質の高いコンテンツは、フォロワーの興味を引き、病院のブランドイメージを向上させる効果があります。
視聴者の満足度を重視することが、SNS活用の成功への第一歩です。
正しく分析・改善が行えていない
正しく分析・改善が行えていないことは、病院のSNS活用における大きな失敗例の一つです。
SNSを運用する際、投稿の効果を測定し、適切な改善を行うことが重要です。
具体的には、どの投稿がどのくらいの反応を得たか、どのような時間帯に多くの閲覧があったか、どんなキーワードで流入を得たのか、などのデータを収集し分析する必要があります。
これにより、次の投稿に活かすことができます。
「どんな内容が患者に響くのか分からない…」と感じる方もいるでしょうが、データに基づいた改善は、投稿の質を高め、患者とのコミュニケーションをより効果的にします。
分析ツールを活用し、定期的な見直しを行うことで、SNS運用の成功に近づけます。
分析と改善のプロセスを怠ることは、せっかくのSNS活用の効果を半減させてしまう恐れがあります。
ターゲットに求められていないコンテンツの発信
ターゲットに求められていないコンテンツの投稿は、病院のSNS運用でよくある失敗の一つです。
例えば、医療に関する専門的な内容ばかりを投稿しても、患者や一般のフォロワーには理解しづらいかもしれません。
その結果、関心を引くことができず、フォロワーが減少するリスクがあります。
SNSを通じて患者との関係を深めたいと思う方もいるでしょう。
そんなときは、患者のニーズや関心をしっかりと把握し、それに応じたコンテンツを提供することが重要です。
具体的には、患者が知りたい情報や役立つ健康アドバイス、病院の取り組みなど、患者目線での情報発信を心がけると良いでしょう。
ターゲットのニーズに合ったコンテンツを提供することで、フォロワーとの関係を強化し、信頼を築くことができます。
以下の記事では医療業界向けに競合のクリニックと差をつけるSNSマーケティング戦略を解説しています。

病院のSNS運用ならユニセントにお任せ
病院のSNS運用で成功を収めるためには、専門的な知識と経験、そして継続することが必要です。
特に、医療領域の分野は競争が激しく、SNSを活用した効果的な集客戦略が重要になっています。

弊社、株式会社ユニセントでは、SNS特化の動画制作からSNS運用コンサルティングを行っております。
- 独自のブランディングで他社との差別化を図りたい
- より効率的かつ効果的に集客をしたい
- コスパ良く動画を制作したい
- SNSを使用して広告費を削減したい
このようなお悩みを抱えているクリニック様は、ぜひ下記よりお問い合わせください。
https://unisent.co.jp/contact/
今なら初回無料でユニセント代表の長尾が直接ヒアリングさせていただき、あなたのクリニックにマッチしたSNS運用戦略や動画制作のポイントをご提案いたします。
ユニセントは、美容医療業界やクリニックの特性を理解し、それぞれのターゲット層に合わせた動画コンテンツ制作を行います。
4000件以上の動画制作や多ジャンルのYouTubeアカウントを0から数十万人規模の登録者にしてきた実績がございます。
また、データ分析を活用した運用改善も行い、常に最適なSNS運用を実現いたします。
SNS運用でお困りの方は是非お気軽にお問い合わせください。
今なら医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
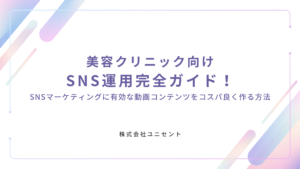
まとめ:病院のSNS活用事例と運用ポイント
今回は、病院のSNS活用に興味を持つ方に向けて、
- SNSを活用した病院の集客方法
- 成功事例の具体的な紹介
- 効果的な運用方法
上記について、筆者の経験を交えながらお話してきました。
病院がSNSを活用することで、患者さんとの距離を縮め、信頼関係を築くことができます。
SNSは情報発信の場としてだけでなく、患者さんからのフィードバックを得る重要なツールです。
多くの病院がSNSを通じて成功を収めているのは、コミュニケーションの質を高め、患者さんのニーズに応えることができたからです。
もし、あなたが今後の集客や患者さんとの関係構築に悩んでいるのであれば、SNS活用を検討してみてはいかがでしょうか。
まずは、小さな一歩から始めましょう。
SNSの活用により、あなたの病院がさらに成長することを応援しています。