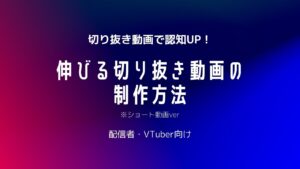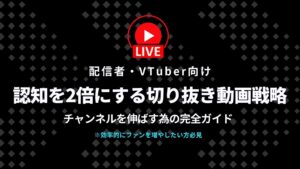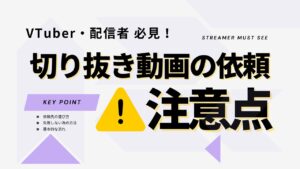医療業界の「集客に最適なSNS活用」とは?失敗しやすいSNS運用の事例も解説

「SNSを使って医院の集客をしたいけど、何から始めればいいのかわからない…」
「医療情報をSNSで発信しても効果があるのか不安…」
そんな悩みを抱える医療関係者は少なくありません。
この記事では、医療機関でSNSを活用した集客や情報発信に関心がある方に向けて、
- 医療業界の集客に最適なSNSプラットフォームの使い方
- 効果的な医療情報の発信方法と患者との信頼関係構築
- 医療機関がSNS運用で陥りやすい失敗とその対策
上記について、解説しています。
SNSは適切に活用すれば、医療機関の認知度向上や新規患者獲得に大きく貢献する強力なツールとなるでしょう。
医療という特殊な分野だからこそ、正しい知識と戦略を持ってSNSに取り組むことが重要です。
この記事を参考に、あなたの医療機関に最適なSNS活用法を見つけてください。
もしあなたがSNSや動画を活用して集客したいとを考えているのであれば、ユニセントへお問い合わせいただくのがおすすめです。
完全無料であなたのクリニックに最適なSNS運用の戦略をご提案いたします。
https://unisent.co.jp/contact/
ユニセントはSNSに特化した動画制作・マーケティングを行なっており、1動画あたり最短1週間で企画・制作・投稿まで完了します。
SNS集客・動画マーケティングに興味がある人はぜひお問い合わせください。
今なら無料で医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料もダウンロードできます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
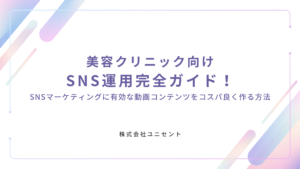
医療業界でSNSを活用するメリット
医療業界でSNSを活用するメリットは、従来の広告手法よりも低コストで効果的な集客が可能になる点です。
医療機関にとってSNSは、地域住民との信頼関係構築や認知度向上に大きく貢献します。
特に若年層や中年層へのアプローチが容易になり、新規患者の獲得につながるでしょう。
例えば、美容クリニックがInstagramで施術事例を紹介したり、小児科がLINEで予防接種の案内をしたりすることで、必要としている患者に直接情報を届けられます。
また、医師の人柄や医院の雰囲気を伝えることで、来院前の不安を軽減する効果も期待できるのです。
以下で詳しく解説していきます。

集客に役立つSNSの効果
医療機関のSNS活用は、効果的な集客ツールとして注目されています。
SNSを活用することで、従来の広告では届かなかった潜在患者層へのアプローチが可能になるでしょう。
特に若年層や情報感度の高い層は、医療機関選びにSNSの情報を参考にする傾向が強まっています。
SNSの大きな魅力は、低コストで広範囲に情報発信できる点です。
医療機関がSNSを集客に活用する主な効果は以下の通りです。
- 地域住民への認知度向上
- クリニックの特徴や診療内容を定期的に発信することで、地域での存在感を高められます。
- 専門性のアピール
- 得意な治療法や最新医療機器の情報を共有し、専門性をわかりやすく伝えられます。
- 患者との信頼関係構築
- 日常の診療風景や医師・スタッフの人柄を伝えることで、来院前の不安を軽減できます。
特に口コミ効果は見逃せません。
満足した患者がSNS上で医療機関の良さを共有すれば、その情報は友人・知人へと拡散していきます。
また、SNSは患者からの質問や相談にも対応できるため、コミュニケーションツールとしても有効です。
以下の記事では病院のSNS活用のメリットとデメリットについてより詳しく解説しています。

診療情報のスムーズな告知
SNSを活用した診療情報の発信は、医療機関にとって効率的な患者とのコミュニケーション手段です。
診療時間の変更や休診日のお知らせ、新しい治療法の導入など、重要な情報をリアルタイムで多くの患者に届けることができます。
従来の院内掲示やホームページ更新だけでは、情報が患者に届くまでに時間がかかっていました。
「大事な休診のお知らせを見逃してしまった…」という患者さんの声も少なくないでしょう。
SNSを活用することで、以下のメリットが生まれます。
- 即時性の高い情報発信
- 急な休診や診療時間変更も、すぐに多くの患者に伝えられます。
- 到達率の向上
- フォロワーのタイムラインに直接表示されるため、情報の到達率が高まります。
- 双方向コミュニケーション
- 患者からの質問や反応を受け取ることで、より良いサービス提供につながります。
特に感染症の流行時期には、混雑状況や予防接種の在庫状況などをリアルタイムで発信することで、患者の来院計画に役立ちます。
また、健康講座や検診キャンペーンなどのイベント告知も効果的です。
事前に周知することで参加者を増やし、地域医療への貢献度を高められます。
SNSを通じた診療情報の発信は、患者サービスの向上と医療機関の業務効率化の両方に貢献する重要なコミュニケーションツールとなっています。
採用に繋がる人材募集
SNSは医療機関の人材採用においても大きな力を発揮します。
特に人材不足が深刻な医療業界では、効果的な採用戦略としてSNSの活用が注目されています。
SNSを通じて医療機関の雰囲気や働きやすさをリアルに伝えることで、求職者の応募意欲を高められます。
「この病院で働いてみたい」と思わせる職場の日常風景や、スタッフの生き生きとした表情が採用に直結するのです。
特に効果的なのは以下の採用コンテンツです。
- スタッフインタビュー
- 実際に働いているスタッフの声は、求職者にとって最も信頼できる情報源となります。
- 職場環境の紹介
- 最新の医療機器や休憩室など、働く環境を視覚的に伝えることで魅力が伝わります。
- 研修制度や福利厚生の紹介
- キャリアアップの機会や働きやすさをアピールできます。
「どんな人と働けるのだろう?」「自分の成長につながる環境なのか?」という求職者の不安を解消するコンテンツが特に効果的です。
また、採用情報だけでなく、日常の診療風景や患者さんとの関わりを発信することで、医療機関としての理念や価値観も伝わります。
これにより、組織の文化に共感する人材を集めやすくなるでしょう。
SNSを活用した人材採用は、単なる求人広告よりも医療機関の魅力を立体的に伝えられる点が最大の強みです。
以下の記事ではクリニック向けにSNS運用・採用の必須スキルのチェックポイントについて詳しく解説しています。

SNS運用の課題と対策
医療業界のSNS運用には、他業種と比較して特有の課題が存在します。
しかし、適切な対策を講じることで、これらの課題を克服し、効果的な運用が可能になるでしょう。
医療機関のSNS運用における最大の課題は、専門性の高い情報発信と患者のプライバシー保護の両立です。
医療情報は正確性が求められる一方で、個人情報の取り扱いには細心の注意が必要となります。
また、日々の診療業務で多忙な医療スタッフが継続的に質の高いコンテンツを作成・投稿することも容易ではありません。
例えば、クリニックのInstagramで患者の治療経過写真を掲載する際には、たとえ許可を得ていても顔が特定されないよう配慮が必要です。
また、医療知識のない広報担当者が専門的な内容を発信すると、誤った情報を広めてしまうリスクもあります。
医療機関のSNS運用における主な課題と対策方法は以下の表を参考にしてみてください。
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 継続運用の難しさ | 投稿スケジュールの事前作成 / 複数スタッフでの分担制 / 外部委託の活用 |
| 専門知識の正確な伝達 | 医師による内容チェック体制の構築 / 専門用語の平易な言い換え / エビデンスに基づいた情報発信 |
| プライバシー保護 | 患者同意書の取得徹底 / 個人特定情報の非掲載 / 写真使用時の細心の注意 |
| 医療広告ガイドライン遵守 | 定期的なガイドライン確認 / 投稿前の法的チェック / 問題事例の社内共有 |
以下で詳しく解説します。

継続運用の難しさを克服する方法
医療機関のSNS運用で最も難しいのは、継続的な更新を維持することです。
多忙な医療現場では、SNS更新が後回しになりがちで、結果的に運用が滞ってしまいます。
「始めたはいいけど、続かなくなってしまった…」という経験をお持ちの方も少なくないでしょう。
継続運用の課題を克服するためには、以下の方法が効果的です。
- 投稿スケジュールの設定
- 週に1回など、無理のない頻度で定期投稿日を決めておくことで習慣化しやすくなります。
- 担当者の明確化
- 複数名で分担するか、専任担当者を決めることで責任の所在を明確にします。
- コンテンツバンクの作成
- 季節の健康情報や予防接種案内など、汎用的な投稿をストックしておきます。
- 外部委託の活用
- リソースに余裕がない場合は、SNS運用の一部または全部を専門会社に委託する選択肢も検討しましょう。
継続的な発信は、患者さんとの信頼関係構築に不可欠です。
最初から完璧を目指すのではなく、小さく始めて徐々に拡大していく戦略が、医療機関のSNS運用では成功への近道となります。
以下の記事では病院のSNS活用事例とSNS運用方法について詳しく紹介しています。

炎上リスクを避けるための注意点
医療機関のSNS運用で最も警戒すべきは炎上リスクです。
一度炎上すると信頼回復に長い時間を要するため、事前の対策が不可欠です。
SNS運用時は患者のプライバシー保護を最優先にしましょう。
「診察室の様子を投稿したい」と思っても、患者が特定される可能性がある画像や情報の投稿は絶対に避けるべきです。
医療広告ガイドラインの遵守も重要です。
誇大広告や比較広告、保証的表現は禁止されています。
炎上を防ぐためのポイントは以下の通りです。
- 投稿前の複数人チェック
- 内容に問題がないか、別の視点からも確認することで誤りを防げます。
- 感情的な返信を避ける
- クレームに対しては冷静に対応し、必要に応じて非公開の場での対応に切り替えましょう。
- 専門用語の使い過ぎに注意
- 「専門的すぎて理解できない…」と感じる患者さんもいるかもしれません。
平易な言葉での説明を心がけてください。
SNSポリシーを明文化し、投稿担当者全員で共有することも効果的です。
何を投稿してよいか、どのような表現を避けるべきかを明確にしておくことで、リスクを大幅に減らせます。
医療広告ガイドラインはこちらからご確認ください↓
医療業界の目的に適したSNSの選び方
医療機関がSNSを活用する際は、目的に合わせた最適なプラットフォーム選びが成功の鍵となります。
各SNSには特性があり、医療機関の目指す成果によって使い分けることで効果的な情報発信が可能になるのです。
例えば、若い患者層へのアプローチにはInstagramやTikTokが効果的である一方、専門的な医療情報の発信にはX(旧Twitter)やYouTubeが適しています。
以下の表は、医療機関の目的別に最適なSNSをまとめたものです
| 目的 | オススメのSNS | 特徴 |
|---|---|---|
| 予約管理 | LINE | 患者との直接コミュニケーションに最適 |
| ビジュアル訴求 | 医院の雰囲気や設備を写真で伝えられる | |
| 動画による情報発信 | YouTube | 詳しい治療説明や医療知識の解説に向いている |
| トレンド発信 | TikTok | 若年層へのリーチに効果的 |
| 専門情報の発信 | X(旧Twitter) | 医療ニュースや最新情報の共有に適している |
| 地域コミュニティ形成 | 地域密着型の医療機関に向いている |
以下で詳しく解説します。

LINEの使い方
LINEは医療機関とユーザーを直接つなぐ強力なツールです。
「友だち追加」を促進することで、予約システムの効率化や診療情報の即時伝達が可能になります。
LINEの活用方法として、まず公式アカウントの開設から始めましょう。
無料プランでも十分な機能が使えるため、初期コストを抑えられるのが魅力です。
「LINE公式アカウントを作るのは難しそう…」と感じる方もいるかもしれませんが、基本的な設定は30分程度で完了します。
LINE活用の具体的なメリットは以下の通りです。
- 予約管理の効率化
- 患者さんがLINEから直接予約できるシステムを構築することで、電話対応の負担を軽減できます。
- リマインダー機能
- 予約日の前日に自動メッセージを送信し、無断キャンセルを減らせます。
- 健康情報の定期配信
- 季節の健康情報や予防接種の案内など、価値ある情報を定期的に届けられます。
- 緊急時の一斉連絡
- 台風や大雪などで診療時間を変更する場合、すぐに全患者さんへ通知できます。
LINE活用で重要なのは、メッセージの頻度とタイミングです。
週1回程度の頻度が理想的で、過度な通知はブロックの原因になりかねません。
また、プライバシーに配慮した運用が医療機関には特に求められます。
個人を特定できる情報や診療内容についてのやり取りは避けるべきでしょう。
LINEは患者さんとの距離を縮め、信頼関係を構築する強力なツールとなります。
Instagramの使い方
Instagramは視覚的なコンテンツが強みのSNSプラットフォームで、医療機関のブランディングに非常に効果的です。
特に医療現場の雰囲気や施設の清潔感、スタッフの親しみやすさを伝えるのに最適なツールといえるでしょう。
「どんな投稿をすればいいのか分からない…」と悩む方も多いかもしれませんが、以下のポイントを押さえれば効果的な運用が可能です。
- ビジュアル重視の投稿
- 診察室や待合室の様子、最新医療機器の紹介など、クリニックの設備や雰囲気が伝わる写真を投稿しましょう。
- ストーリーズの活用
- 日常的な出来事や、スタッフの人柄が伝わる短い動画コンテンツを定期的に投稿することで親近感を醸成できます。
- ハッシュタグ戦略
- 地域名や症状、治療法などの関連ハッシュタグを適切に使用することで、潜在患者からの発見可能性が高まります。
- リール機能の活用
- 短時間で健康情報や予防法を伝える動画コンテンツは、特に若年層へのリーチに効果的です。
投稿する内容は医療の専門性を保ちつつも、難しい専門用語は避け、患者目線の分かりやすい表現を心がけることが重要です。
Instagramは特に20〜40代の女性ユーザーが多いため、家族の健康管理を担うことが多いこの層へのアプローチとして最適なSNSといえます。
以下の記事ではクリニックのインスタグラム運用で集客や採用に繋げる方法について詳しく解説しています。
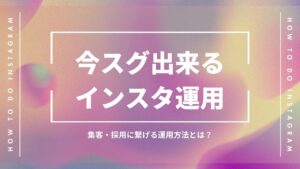
YouTubeの使い方
YouTubeは医療機関にとって強力な情報発信ツールです。
動画コンテンツによる詳細な説明が可能なため、治療法や医療知識の普及に最適です。
YouTubeを医療分野で活用する主なメリットは以下の通りです。
- 視覚的な説明力
- 診療内容や医療機器、施術方法などを映像で分かりやすく伝えられます。
- 「百聞は一見にしかず」の言葉通り、文字や写真だけでは伝わりにくい内容も動画なら理解されやすいでしょう。
- 診療内容や医療機器、施術方法などを映像で分かりやすく伝えられます。
- 長時間の視聴が可能
- 他のSNSと比べて長い尺の動画が投稿できるため、詳細な医療情報を提供できます。
- 検索エンジンとしての側面
- YouTubeは世界第2位の検索エンジンとも言われており、医療情報を探すユーザーに直接アプローチできます。
効果的なコンテンツとしては、診療内容の解説、よくある質問への回答、医師によるヘルスケアアドバイスなどが挙げられます。
動画制作には一定の手間がかかりますが、一度作成すれば長期間にわたって視聴される資産となります。
定期的な投稿と専門性の高いコンテンツ作りを心がければ、医療機関の信頼構築と集客に大きく貢献するでしょう。
以下の記事ではクリニックのYouTube運用テクニックとYouTubeが伸びない時の対策について解説しています。

TikTokの使い方
TikTokは若年層を中心に爆発的な人気を誇るショートムービープラットフォームです。
医療機関がTikTokを活用することで、若い世代へのアプローチや親しみやすいクリニックイメージの構築が可能になります。
TikTokの特徴は15秒から60秒程度の短い動画で情報を伝えられる点にあります。
この特性を活かした医療機関の効果的な使い方には以下のようなものがあります。
- 健康豆知識の発信
- 短時間で伝わりやすい健康情報や予防医学のアドバイスを提供することで、視聴者の健康意識向上に貢献できます。
- 施設や設備の紹介
- クリニック内部の様子や最新医療機器を紹介することで、来院前の不安を軽減できます。
- スタッフの人柄アピール
- 医師やスタッフの人間味あふれる一面を見せることで、「行きやすいクリニック」という印象を与えられます。
「堅苦しい医療機関のイメージを払拭したい…」と考えている方にとって、TikTokは非常に有効なツールとなるでしょう。
TikTok運用のポイントは、専門知識をわかりやすく伝えながらも、エンターテイメント性を忘れないことです。
流行のBGMやエフェクトを取り入れつつ、医療の専門性と信頼性のバランスを保った投稿を心がけましょう。
医療情報の発信においては、プライバシーや医療倫理に十分配慮した内容選定が不可欠です。
以下の記事ではクリニックのTikTok活用事例と運用方法について紹介しています。

X(旧Twitter)の使い方
X(旧Twitter)は医療情報の迅速な発信と専門家同士の交流に最適なプラットフォームです。
文字数制限があるため、簡潔な医療情報や診療案内を発信できます。
「今日から花粉症の薬を処方開始しました」といった短い告知が効果的でしょう。
患者さんの声を拾いやすく、地域の健康ニーズを把握するリサーチツールとしても活用できます。
医療専門家とのネットワーク構築にも優れており、学会情報の共有や最新研究のディスカッションの場として機能します。
効果的な運用のポイントは以下の通りです。
- ハッシュタグの活用
- 医療や健康に関連するハッシュタグを付けることで、関心のあるユーザーに情報が届きやすくなります。
- 定期的な投稿
- 週2〜3回程度の定期投稿で、フォロワーとの関係性を維持しましょう。
- 専門性と親しみやすさのバランス
- 専門用語を避け、わかりやすい表現を心がけつつも、医療機関としての信頼性を保つことが重要です。
「難しい医療情報をどう伝えればいいか悩んでいる…」という方も多いかもしれません。
そんな時は、患者さんからよく受ける質問をQ&A形式で投稿するのが効果的です。
X(旧Twitter)は即時性が高く、医療情報の迅速な発信に適したSNSといえます。
Facebookの使い方
Facebookは医療機関にとって多世代へのアプローチと情報発信の両立が可能なSNSです。
特に40代以上の利用者が多く、地域密着型の医療機関には最適なプラットフォームといえるでしょう。
Facebookの効果的な活用法は以下の通りです。
- 診療案内や健康情報の定期投稿
- 地域住民に役立つ季節の健康情報や、診療内容の詳細な説明を投稿することで信頼関係を構築できます。
- イベント機能の活用
- 健康セミナーや無料相談会などのイベントを告知し、参加者を募ることができます。
- 地域コミュニティとの連携
- 地域の他の事業者や団体と連携した投稿で、地域に根差した医療機関としての印象を強められます。
「Facebookは難しそう…」と感じる方も多いかもしれませんが、実は投稿の作成から予約投稿まで比較的シンプルな操作で行えます。
Facebookでは詳細なプロフィール情報を設定できるため、医院の理念や医師の経歴など、じっくり読んでもらいたい情報の発信に適しています。
また、Facebookグループを作成して患者コミュニティを形成することで、オンライン上での患者同士の交流の場を提供することも可能です。
投稿の際は専門用語を避け、一般の方にもわかりやすい表現を心がけましょう。
医療機関におすすめのSNS運用法
医療機関がSNSを効果的に活用するには、患者目線のコンテンツ制作と継続的な情報発信が鍵となります。
SNSは単なる宣伝ツールではなく、患者との信頼関係を構築するためのコミュニケーションチャネルとして捉えるべきでしょう。
医療機関の強みや特色を活かしたコンテンツを定期的に発信することで、潜在的な患者に対して専門性をアピールできます。
具体的には、以下のポイントを押さえたSNS運用がおすすめです。
- 診療科目や得意分野に関する専門的情報の発信
- 医師や医療スタッフの人柄が伝わる投稿
- 季節の健康情報や予防医学に関するアドバイス
- 施設の設備や衛生管理への取り組み紹介
- 患者からの質問に対する一般的な回答(個別診療ではない形で)
- 地域の健康イベントや健診情報の告知
患者が本当に知りたい情報と、医療機関として伝えるべき情報のバランスを取りながら、
専門性と親しみやすさを両立させた運用を心がけましょう。
以下で詳しく解説します。

クリニックのブランディングにSNSを活用
SNSは医療機関のブランディングに欠かせないツールとなっています。
クリニックの特色や強みを効果的に発信することで、他院との差別化を図り、選ばれる医療機関になることができるのです。
SNSを活用したブランディングでは、まず自院の「強み」を明確にすることが重要です。
「どんな症状に強いのか」「どんな設備が充実しているのか」「どんな医師がいるのか」など、患者さんが知りたい情報を整理しましょう。
「うちのクリニックの特徴って何だろう…」と悩む方もいるかもしれません。
そんな時は患者さんの声を集めてみると良いでしょう。
効果的なクリニックブランディングのポイントは以下の通りです。
- 一貫したメッセージ
- 診療方針や理念を一貫して発信することで、クリニックのイメージが定着します。
- ビジュアルの統一
- ロゴや色使い、写真のトーンなどを統一し、記憶に残るデザインを心がけましょう。
- 患者さんの声の活用
- 実際の治療体験や感想を紹介することで、信頼性が高まります。
- 地域性の強調
- 地域に根ざした医療機関であることをアピールし、親近感を持ってもらいましょう。
SNSでのブランディングは、単なる宣伝ではなく「価値提供」の場と捉えることが大切です。
健康情報や予防医学の知識など、フォロワーにとって有益な情報を発信することで、自然と信頼関係が構築されていきます。
クリニックのブランディングにSNSを活用する際は、長期的な視点で一貫した発信を続けることが成功への鍵となります。
ドクター個人の魅力を伝える方法
ドクター個人の魅力を伝えることは、医療機関のSNS活用において非常に効果的な戦略です。
患者さんは病院そのものよりも、実際に診療する医師の人柄や専門性に安心感を抱くことが多いものです。
SNSを通じて医師の人間性を見せることで、「この先生なら信頼できる」と思ってもらえる関係性を構築できます。
効果的なドクター個人の魅力発信方法には以下のようなものがあります。
- 専門分野の解説動画
- 医学的知識をわかりやすく説明する短い動画は、専門性と教育力をアピールできます。
- 診療現場の雰囲気紹介
- 実際の診療風景(患者のプライバシーに配慮した上で)を共有し、通院への不安を軽減します。
- 学会参加や研修報告
- 最新の医療知識を学ぶ姿勢を見せることで、常に向上心を持った医師であることを伝えられます。
「どんな内容を投稿すればいいか悩む…」という声もよく聞かれますが、
まずは自分が患者として知りたいと思う情報から始めるとよいでしょう。
ただし、プライベートの共有は程よい距離感を保つことが重要です。
医師としての品位を保ちながら、人間味のある発信を心がけましょう。
以下の記事では医療業界のYouTube運用で今すぐ成果を出す実践ステップについて解説しています。

医療業界のSNS活用に関するよくある失敗例
医療業界でSNSを効果的に活用するには、よくある失敗パターンを理解し回避することが重要です。
多くの医療機関が陥りがちな失敗には、明確な戦略なしにSNSを始めてしまうことがあります。
特に医療という専門性の高い分野では、闇雲な情報発信は逆効果になりかねません。
これは患者からの信頼低下にもつながる事例です。
以下に医療機関がSNSで失敗しやすい主な特徴をまとめました。
- 医療情報の正確性に欠ける投稿
- プライバシーへの配慮不足
- 専門用語の多用による一般患者の理解困難
- 投稿の一貫性がなく、ブランドイメージが定まらない
- 患者からの質問やコメントへの返信遅延
- 医療広告ガイドラインへの違反
- 競合他院の批判や比較
- 効果や症例の過度な強調
これらの失敗を避けるためには、SNS運用の目的を明確にし、ターゲットとなる患者層を意識した計画的な投稿戦略を立てることが大切です。

一貫性のない投稿
医療機関のSNS運用で最も失敗しやすいのが、一貫性のない投稿です。
今日は医療情報、明日は院内イベント、次は全く関係ない内容という具合に投稿内容がバラバラでは、フォロワーが何を期待して見ればよいのか混乱してしまいます。
「この医療機関はどんな情報を発信してくれるのだろう」と期待してフォローしたユーザーが、全く異なる内容ばかり目にすると離脱してしまうでしょう。
一貫性を保つためには、まず明確なコンセプトを決めることが重要です。
例えば以下のようなテーマに絞ることで、フォロワーの期待に応える発信ができます。
- 専門分野に関する健康情報
- 定期的に同じカテゴリの情報を提供することで、専門性をアピールできます。
- 診療案内や予防医療の啓発
- 季節の健康情報など、患者さんに役立つ情報を計画的に発信します。
- スタッフや院内の雰囲気紹介
- 親しみやすさを伝えるコンテンツを定期的に盛り込みます。
「毎週水曜日は健康コラム、金曜日はスタッフ紹介」など、曜日ごとに投稿内容を決めておくと、一貫性を保ちやすくなります。
一貫したSNS運用は、医療機関としての信頼性向上にも直結します。
ターゲットとなる患者層を明確にし、その層に価値ある情報を継続的に提供することが成功への鍵となるのです。
以下の記事では医療業界の集客で失敗を避けるためのポイントを詳しく紹介しています。

投稿頻度が不安定
投稿頻度の不安定さは、医療機関のSNS運用において最も頻繁に見られる失敗例の一つです。
最初は意気込んで毎日投稿していたのに、徐々に間隔が空き、気づけば数ヶ月更新していないというパターンは珍しくありません。
「忙しくて更新する時間がない…」と感じている医療関係者も多いのではないでしょうか。
不規則な投稿頻度がもたらす最大の問題は、フォロワーとの信頼関係の構築が難しくなることです。
SNSのアルゴリズムは、定期的に投稿するアカウントを優遇する傾向があります。
投稿頻度が不安定だと、せっかくの情報が患者さんの目に触れる機会が減少してしまいます。
この問題を解決するためには、以下の対策が効果的です。
- 投稿カレンダーの作成
- あらかじめ月単位で投稿内容と日程を計画しておくことで、継続的な運用が可能になります。
- 投稿の一括作成
- まとまった時間が取れる日に複数の投稿を作成し、予約投稿機能を活用しましょう。
- 無理のない頻度設定
- 週1回など、確実に続けられる頻度から始めることが長期的な運用のコツです。
- 外部の制作会社やSNS運用代行会社に依頼
- 自院でコンテンツ制作やSNS運用のリソースがない場合はプロに依頼しましょう。
投稿頻度の安定化は、医療機関のSNS運用成功への第一歩となります。
以下の記事では医療業界の動画制作依頼で失敗しない為に確認すべきポイントについて解説しています。

クオリティが低い
SNSの投稿クオリティが低いと、医療機関の信頼性を大きく損なう可能性があります。
特に医療という専門性と信頼が重要な分野では、投稿の質が直接ブランドイメージに影響します。
「せっかく情報発信しているのに反応が悪い…」と感じている医療機関は、投稿の質を見直してみましょう。
クオリティの低い投稿には以下の特徴があります。
- 画像がぼやけている
- スマートフォンで急いで撮影した写真や、解像度の低い画像は専門性の高い医療機関としての印象を損ねます。
- 文章に誤字脱字が多い
- 医学的な正確さが求められる医療機関で、基本的な文章ミスが多いと信頼性が低下します。
- デザインに一貫性がない
- 投稿ごとにフォントやカラーが異なると、ブランドイメージが定着しません。
質の高い投稿を作るためには、基本的なデザインテンプレートを作成し、統一感を持たせることが重要です。
また、投稿前には必ず複数の目でチェックする体制を整えましょう。
医療情報は正確さが命です。
間違った情報や不適切な表現は患者さんの健康に関わる可能性もあるため、投稿内容の精査は特に慎重に行う必要があります。
専門性が薄い
医療関連のSNSで専門性が薄い投稿は、かえって信頼を損なう結果になります。
医療情報は命に関わる重要な内容であるため、専門的な知見に基づいた正確な情報発信が不可欠です。
専門性の薄い投稿の特徴として、一般的な健康情報の引用だけで具体的な根拠や出典が示されていない点が挙げられます。
また、医療従事者としての専門的視点が欠如し、インターネット上の情報をそのまま転載しているケースも見受けられます。
「専門家なのに基本的な内容しか発信していない…」と感じる患者さんも少なくないでしょう。
このような状況を改善するためには、以下の対策が効果的です。
- 自院の専門分野に特化した情報発信
- 医院やクリニックの強みとなる診療科目や治療法について詳しく解説しましょう。
- エビデンスに基づいた情報提供
- 最新の研究結果や医学的根拠を示しながら情報を発信することで信頼性が高まります。
- 専門用語の適切な解説
- 難しい医療用語をわかりやすく説明し、患者目線の情報発信を心がけましょう。
専門性の高い投稿は、医療機関としての信頼構築に直結します。
SNSでの発信は、単なる集客ツールではなく、医療知識の普及という社会的役割も担っているのです。
以下の記事ではクリニックの集客における「動画とSEO」の重要性について解説しています。

医療業界のSNS活用ならユニセントへお任せ
医療業界のSNS運用で集客を成功させるためには、専門的な知識と経験、そして継続することが必要です。
特に、医療領域の分野は競争が激しく、SNSを活用した効果的な集客戦略が重要になっています。

弊社、株式会社ユニセントでは、SNS特化の動画制作からSNS運用コンサルティングを行っております。
- 独自のブランディングで他社との差別化を図りたい
- より効率的かつ効果的に集客をしたい
- コスパ良く動画を制作したい
- SNSを使用して広告費を削減したい
このようなお悩みを抱えているクリニック様は、ぜひ下記よりお問い合わせください。
https://unisent.co.jp/contact/
今なら無料でユニセント代表の長尾が直接ヒアリングさせていただき、あなたのクリニックにマッチしたSNS運用戦略や動画制作のポイントをご提案いたします。
ユニセントは、4000件以上の動画制作や多ジャンルのYouTubeアカウントを0から数十万人規模の登録者にしてきた実績がございます。
医療業界・クリニックの特性を理解し、それぞれのターゲット層に合わせた動画コンテンツ制作を行います。
また、データ分析を活用した運用改善も行い、常に最適なSNS運用を実現いたします。
SNS運用でお困りの方は是非お気軽にお問い合わせください。
今なら医療業界向けにSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法についてまとめたお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
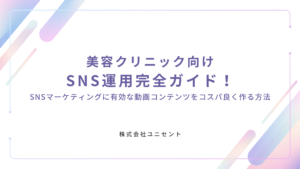
まとめ:医療機関のSNS活用で成功する秘訣
今回は、医療機関のSNS活用に興味を持ち、効果的な集客方法を模索している方に向けて、
- 医療機関の集客に最適なSNSプラットフォームの使い方
- 医療機関のSNS運用における失敗しやすいポイント
- 患者との信頼関係を構築するSNSコンテンツ戦略
上記について、解説してきました。
医療機関がSNSを活用する際は、目的に合ったプラットフォームを選び、一貫した情報発信を行うことが重要です。
特にInstagramやYouTubeは視覚的な訴求力や即時性に優れており、医療機関の特色を伝えるのに適しています。
日々の業務に追われる中で、SNS運用まで手が回らないと感じる医療関係者も多いことでしょう。
SNS運用を成功させるためには、無理なく継続できる投稿頻度を設定し、プライバシーに配慮した上で、
患者さんの悩みに寄り添うコンテンツを提供することが大切です。
運用担当者を明確にし、投稿ガイドラインを設けることで、一貫性のある情報発信が可能になるでしょう。
SNSの活用によって、医療機関と患者さんとの距離は確実に縮まります。
正しい情報を発信し続けることで、地域における信頼される医療機関としての地位を確立できるでしょう。
まずは自院の強みを活かしたSNS戦略を立て、小さな一歩から始めてみましょう。
患者さんの健康を支える医療機関だからこそ、SNSを通じた温かみのあるコミュニケーションが、あなたの医療機関の新たな魅力となることを願っています。