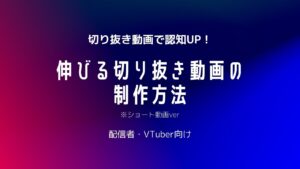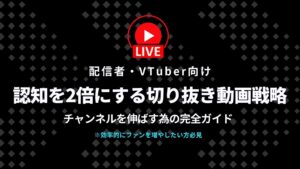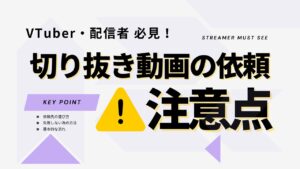病院のSNS活用の「メリット・デメリット」と「各SNSの特徴・効果」まで解説
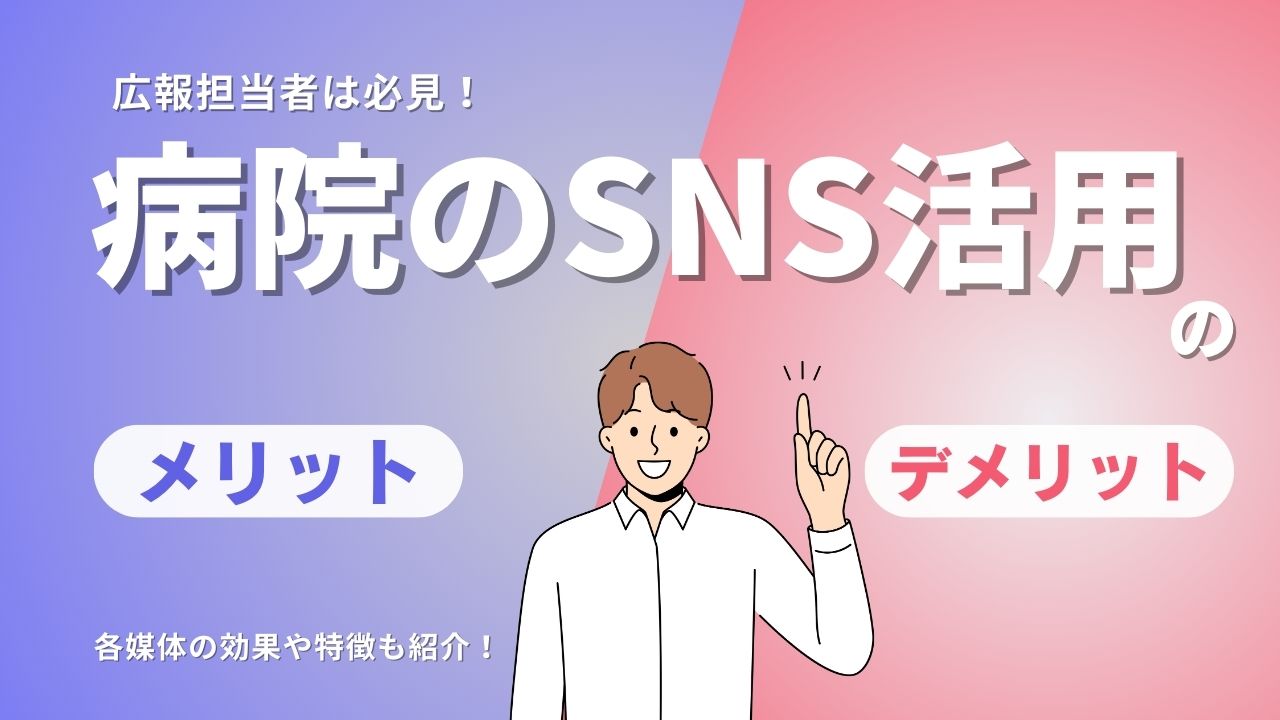
最近、病院がSNSを活用することが増えてきましたが、「本当に効果があるのかな…」と疑問に思う方もいるでしょう。
また、「SNSを使うことで患者さんとのトラブルにならないかな…」と心配する方もいるかもしれません。
SNSの活用にはメリットもデメリットも存在しますが、正しい知識を持つことで、これらを上手に活かすことが可能です。
この記事では、病院のSNS活用に興味がある方に向けて、
- 病院がSNSを活用するメリット
- SNS活用のデメリットと注意点
- 各SNSの効果と特徴
上記について、解説しています。
SNSを上手に活用することで、病院の知名度を上げたり、患者さんとのコミュニケーションを円滑にすることができます。
しかし、誤った使い方をすると、逆にトラブルを招くこともあるため、この記事を参考にして、SNSの活用方法をしっかりと理解してください。
もしあなたがSNS活用を考えているのであれば、ユニセントへ一度お問い合わせいただくのがおすすめです。
今なら30分の無料相談もご用意しているので、SNS集客・動画マーケティングに興味がある人はぜひお問い合わせください。
https://unisent.co.jp/contact/
ユニセントはSNSに特化した動画制作・マーケティングを行なっており、1動画あたり最短1週間で企画・制作・投稿まで完了します。
あなたのクリニックに最適なSNS運用プランを無料でご提案いたします。
今なら医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
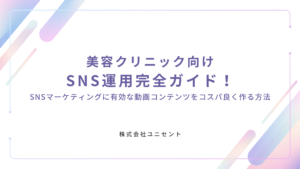
病院がSNSを活用するメリットとは?
病院がSNSを活用するメリットは多岐にわたります。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 無料で手軽に始められる
- 患者数増加に貢献する可能性がある
- ブランディング強化に繋がる
- リアルタイムに告知できる
- 患者とのコミュニケーションツールになる
まず、無料で手軽に始められることが大きな利点です。
SNSプラットフォームは基本的に無料で利用でき、初期投資が少なくて済むため、予算が限られている病院でも導入しやすいでしょう。

また、SNSを通じて患者数の増加が期待できます。
情報を広く発信することで、地域の新規患者の獲得や既存患者のリテンションに役立ちます。
さらに、SNSは病院のブランディングを強化する手段としても有効です。
専門的な情報や医師の紹介、病院の取り組みなどを発信することで、信頼性や専門性をアピールできます。
例えば、定期的な健康情報の発信やイベント告知を行うことで、地域社会との結びつきを強めることができます。
以下で詳しく解説していきます。
無料・手軽に始められる
無料で手軽に始められることは、病院がSNSを活用する大きなメリットです。
SNSは基本的にアカウントを作成するだけで利用開始でき、初期費用がかからないため、広告費用を抑えたい病院には最適です。
特に中小規模の病院にとって、限られた予算で効果的な情報発信が可能になるのは大きな魅力でしょう。
また、SNSはスマートフォンやパソコンから簡単に操作できるため、特別な技術がなくても運用しやすいです。
これにより、医療スタッフが日常業務の合間に情報発信を行うことも可能です。
「SNSを使ってみたいけど、難しそう…」と感じる方も多いかもしれませんが、実際にはとても手軽に始められます。
さらに、SNSを通じて患者や地域住民に直接情報を届けることができるため、病院の認知度向上や患者数の増加にも繋がります。
これらの要素が組み合わさることで、病院の情報発信力が強化され、より多くの人々にアプローチできるのです。
無料で手軽に始められるSNS活用は、病院の情報発信戦略において非常に有効な手段と言えるでしょう。
患者数増加に貢献する可能性がある
病院がSNSを活用することで、患者数の増加に貢献する可能性があります。
SNSを通じて情報を発信することで、地域の住民や潜在的な患者に対して病院の存在をアピールできます。
特に、健康に関する情報や医療サービスの紹介などを定期的に発信することで、信頼感を築きやすくなります。
「新しい病院を探しているけれど、どこが良いのだろう?」と感じている方にとって、SNSでの情報は非常に参考になるでしょう。
また、SNSを通じて病院の最新情報やイベント、キャンペーンなどをリアルタイムで伝えることができるため、患者の関心を引きやすくなります。
これにより、来院のきっかけを増やすことが可能です。
さらに、患者からのフィードバックを受け取りやすくなるため、サービスの向上にも役立ちます。
SNSを活用することで、病院の情報を広く発信し、地域社会とのつながりを強化し、患者数の増加に貢献できるのです。
ブランディング強化に繋がる
病院がSNSを活用することで、ブランディング強化に繋がる理由は明確です。
SNSは多くの人々に情報を発信できるため、病院の理念や特色を広く伝えることができます。
例えば、「地域密着型の医療を提供している病院」としてのイメージをSNSで発信することで、地域住民に親しみやすい存在として認識されるでしょう。
また、患者からの口コミや評価もSNS上で広がるため、信頼性の向上にも寄与します。
さらに、定期的な情報発信により、病院の最新の取り組みやサービスをアピールできるのも大きな利点です。
これにより、患者だけでなく地域社会全体に対しても、病院の存在感を強めることが可能です。
結果として、SNSは病院のブランド価値を高め、競争力を向上させる重要なツールとなります。
リアルタイムに告知できる
病院がSNSを活用する際の大きなメリットの一つは、リアルタイムに告知できる点です。
これにより、急な診療時間の変更や新しいサービスの開始、イベントの告知などを即座に患者やフォロワーに伝えることができます。
例えば、インフルエンザの流行期に予防接種の予約状況や空き情報を迅速に知らせることで、患者の利便性を高めることができるでしょう。
「急に診療時間が変わったけど、どうやって患者に知らせよう…」と悩むこともなくなります。
リアルタイムで情報を発信することで、患者との信頼関係を築きやすくなり、病院の信頼度を向上させることが可能です。
しかし、情報の正確性には細心の注意を払う必要があります。
誤った情報が広まると、信頼を損なうリスクもあるため、投稿前の確認は必須です。
このように、SNSは病院にとって即時性と信頼性を兼ね備えた有効なコミュニケーションツールとなります。
患者とのコミュニケーションツールになる
病院がSNSを活用する際、患者とのコミュニケーションツールとしての役割が非常に重要です。
SNSを通じて患者からの質問や意見をリアルタイムで受け取ることができ、迅速な対応が可能になります。
「病院に直接行くのはちょっと…」と感じる方も、SNSなら気軽に問い合わせができるでしょう。
また、病院側も日常的な健康情報や予防策、診療時間の変更などを迅速に発信できます。
これにより、患者と病院の信頼関係を築くことができ、患者の満足度も向上するでしょう。
さらに、患者からのフィードバックを活用することで、サービスの改善にも役立ちます。
SNSは、双方向のコミュニケーションを可能にし、病院と患者の距離を縮める有効な手段です。
病院がSNSを活用する際のデメリット
病院がSNSを活用する際のデメリットとして、挙げられる項目は以下の通りです。
- 誤情報の拡散・炎上リスク
- 効果的なSNS運用には知識や時間が必要
- 成果が出るまで時間がかかる

まず誤情報の拡散や炎上リスクが挙げられます。
SNSは情報が瞬時に広がるため、誤った情報が拡散されると病院の信用に大きな影響を及ぼします。
また、SNS上でのトラブルが炎上に繋がることもあり、対応に追われることがあります。
次に、SNS運用にはコンテンツ制作などの知識や時間が必要です。
効果的な投稿を行うためには、医療に関する正確な情報提供や視覚的に魅力的なコンテンツ作成が求められます。
これには専門的な知識とスキルが必要で、スタッフの負担が増える可能性があります。
例えば、SNSでの投稿が増えると、スタッフが日常業務の合間にコンテンツを作成しなければならないことがあります。
さらに、SNSの成果が出るまでには時間がかかる場合が多く、短期間での効果を期待することは難しいかもしれません。
以下で詳しく解説していきます。
誤情報の拡散・炎上リスク
誤情報の拡散や炎上リスクは、病院がSNSを活用する際に避けられないデメリットの一つです。
SNSは情報が瞬時に広がるため、誤った情報が一度流れるとすぐに多くの人に伝わり、収拾がつかなくなることがあります。
「この情報は本当に正しいのだろうか…」と不安に思う方もいるでしょう。
特に医療に関する情報は、正確性が求められるため、誤情報が広まると病院の信頼を損なう可能性があります。
また、炎上はSNS上での批判や否定的なコメントが急増する現象で、これも病院にとって大きなリスクです。
炎上は一度起こると、対応に多くの時間と労力が必要となり、病院の評判にも悪影響を及ぼします。
このリスクを軽減するためには、情報発信前に必ず内容を確認し、複数のスタッフでチェックする体制を整えることが重要です。
また、炎上が発生した場合には、迅速かつ誠実に対応することが求められます。
これにより、誤情報の拡散や炎上のリスクを最小限に抑え、病院の信頼性を維持することが可能です。
効果的なSNS運用には知識や時間が必要
病院がSNSを活用する際のデメリットの一つとして、SNS運用のコンテンツ制作などの知識や時間が必要であることが挙げられます。
SNSは手軽に始められる反面、効果的な運用を行うためには専門的な知識が不可欠です。
たとえば、投稿する内容は医療に関する正確な情報であるべきですし、視覚的に魅力的な写真や動画の作成も求められるでしょう。
さらに、投稿のタイミングや頻度、フォロワーとのコミュニケーション方法なども考慮する必要があります。
「SNSを始めてみたものの、何を投稿すればいいのか分からない…」と感じる方もいるかもしれません。
また、これらの作業には時間がかかるため、日々の業務と並行して行うのは大変です。
したがって、SNS運用を担当するスタッフに対して、適切な教育やサポートを行うことが重要です。
最終的に、知識や時間の投資が必要であることを理解し、計画的に運用することで、SNSの効果を最大限に引き出すことが可能になります。
成果が出るまで時間がかかる
病院がSNSを活用する際、成果が出るまで時間がかかることがあります。
これは、SNS運用が即効性のある手段ではなく、継続的な努力が必要だからです。
例えば、フォロワー数の増加や患者の来院数の増加は、地道な情報発信とコミュニケーションの積み重ねによって実現します。
しかし、継続的に運用することで、病院の認知度や信頼度が徐々に高まります。
また、SNSのアルゴリズムやトレンドに対応したコンテンツの作成も重要です。
これにより、フォロワーとのエンゲージメントが向上し、最終的には病院のブランディングや集客に貢献します。
短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点でSNS運用を考えることが成功の鍵です。
以下の記事ではクリニックの集客戦略やブランディングについて解説しています。

病院で活用できるSNSとその特徴
病院で活用できるSNSは、
- LINE公式アカウント
- X(旧Twitter)
- Instagram(インスタグラム)
- TikTok(ティックトック)
- Facebook(フェイスブック)
- YouTube(ユーチューブ)
などがあります。

それぞれのSNSは異なる特性を持ち、病院の目的やターゲット層に応じて選択することで、効果的な情報発信が可能です。
SNSの特性を理解し、適切に活用することで、患者とのコミュニケーションが円滑になり、病院の認知度向上やブランド力強化につながるでしょう。
例えば、LINE公式アカウントは、患者との直接的なコミュニケーションや予約管理に適しています。
Xは、短いメッセージで情報を迅速に拡散できるため、緊急時の告知に役立ちます。
Instagramはビジュアル重視のため、病院の雰囲気や設備を視覚的にアピールするのに適しています。
Facebookは、幅広い年齢層にリーチできるため、幅広い情報発信が可能です。
YouTubeは、動画を通じて医療情報や病院紹介を詳しく伝えることができます。
以下で詳しく解説していきます。
LINE公式アカウント
LINE公式アカウントは、病院にとって非常に有用なSNSツールです。
まず、LINEは日本国内で広く使われているメッセージアプリであり、多くの患者が日常的に利用しています。
このため、LINE公式アカウントを活用することで、患者とのスムーズなコミュニケーションが可能になります。
たとえば、診療時間の変更や休診情報などをリアルタイムで通知できるため、患者の利便性が向上します。
また、LINE公式アカウントは、予約システムと連携させることで、患者が簡単に診療の予約や変更を行えるようになります。
これにより、電話対応の負担を軽減し、スタッフの業務効率を向上させることができます。
さらに、LINE公式アカウントはクーポンやキャンペーン情報を配信するのにも適しています。
これにより、病院のサービスを効果的にアピールし、新規患者の獲得や既存患者のリピートを促進することが可能です。
LINE公式アカウントを活用することで、病院は患者とのコミュニケーションを円滑にし、業務効率を向上させることができます。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は、病院がSNSを活用する際に非常に有効なツールです。
まず、Xはリアルタイムで情報を発信できるため、緊急のお知らせやイベント情報などを迅速に広めることができます。
さらに、ハッシュタグを利用することで、特定のトピックに興味を持つユーザーにアプローチしやすくなります。
このため、地域の健康イベントやキャンペーンを広めたいときに非常に効果的です。
一方で、Xの特性として、情報が拡散しやすい反面、誤情報が広がるリスクも伴います。
「誤解されるかもしれない…」と不安に感じる方もいるでしょう。
しかし、適切な情報管理と迅速な対応を心がけることで、信頼性を維持することが可能です。
Xは、短いメッセージでインパクトを与えることができるため、病院の最新情報や健康に関する豆知識を手軽に発信するのに適しています。
このように、Xは情報の即時性と拡散力を活かし、病院の認知度向上や患者とのコミュニケーション強化に貢献します。
Instagram(インスタグラム)
Instagram(インスタグラム)は、視覚的なコンテンツを中心に展開するSNSで、特に若年層や女性に人気があります。
病院がInstagramを活用することで、視覚的な情報を通じて施設の雰囲気や医療スタッフの紹介、治療の様子などを効果的にアピールできます。
これにより、患者が病院の雰囲気を事前に知ることができ、安心感を持って来院することが期待できます。
また、ストーリーズ機能を活用することで、日常の小さな出来事や最新情報をリアルタイムで発信可能です。
この機能は24時間で消えるため、気軽に情報を発信できるのも魅力です。
「病院の内部をもっと知りたい…」と思っている方には、特に親しみやすいツールと言えるでしょう。
ただし、写真や動画の質が重要となるため、コンテンツ制作には一定のスキルが必要です。
また、コメントへの対応やフォロワーとのコミュニケーションも重要なため、運用には時間と労力がかかります。
したがって、運用体制を整えた上で、計画的に活用することが成功の鍵と言えます。
以下の記事ではクリニックのインスタグラムの活用事例を紹介しています。

TikTok(ティックトック)
TikTokは、特に若年層をターゲットとした病院のプロモーションにおいて、非常に効果的なSNSプラットフォームです。
このプラットフォームは、短い動画を通じて視覚的に訴求することができ、病院の雰囲気やスタッフの人柄、治療の流れなどを親しみやすく伝えることが可能です。
たとえば、病院の紹介動画や健康に関する豆知識を楽しく伝えることで、フォロワーに安心感を与えつつ、健康意識を高めることができます。
また、TikTokのアルゴリズムはユーザーの興味に基づいてコンテンツを推薦するため、適切なハッシュタグやトレンドを活用すれば、広範囲にリーチすることが可能です。
しかし、注意が必要なのは、情報の正確性と倫理的な配慮です。
医療情報を発信する際は、必ず専門家の監修を受け、誤解を招かないようにすることが重要です。
さらに、TikTokではユーザーとのインタラクションが活発であるため、コメントやダイレクトメッセージを通じて患者とのコミュニケーションを強化することもできます。
これにより、患者の疑問や不安を解消し、信頼関係を築くことができるでしょう。
病院のSNS活用において、TikTokは新しい可能性を広げるツールとして注目されています。
以下の記事ではクリニックのTikTokの成功事例を紹介しています。

Facebook(フェイスブック)
Facebook(フェイスブック)は、病院がSNSを活用する際に非常に有効なツールの一つです。
まず、Facebookの最大の特徴は、幅広い年齢層にアプローチできる点です。
特に中高年層が多く利用しているため、この層に向けた情報発信には最適です。
例えば、健康セミナーの告知や、病院の新しい取り組みを紹介することで、地域の認知度を高めることができます。
また、Facebookは投稿のシェア機能が充実しており、情報が拡散しやすいというメリットがあります。
これにより、病院の情報を多くの人々に届けることが可能です。
しかし、情報が拡散しやすいということは、誤情報が広まるリスクも伴います。
このため、投稿内容は慎重に選び、正確な情報を提供することが重要です。
さらに、Facebookのコメント機能を活用すれば、患者や地域住民との双方向のコミュニケーションが可能になります。
これにより、病院への信頼感を高め、患者との関係を深めることができるでしょう。
Facebookは、病院の情報発信とコミュニケーション強化において、非常に効果的なSNSです。
YouTube(ユーチューブ)
YouTube(ユーチューブ)は、病院がSNSを活用する際に非常に有効なプラットフォームです。
動画を通じて視覚的に情報を伝えることができるため、患者にとって理解しやすいからです。
例えば、病院の施設紹介や医師のインタビュー、健康に関する情報提供など、さまざまなコンテンツを作成できます。
「動画で見れば、より安心できるかもしれない…」と感じる患者も多いでしょう。
また、YouTubeは検索エンジンとしても利用されており、病院の動画が多くの人に見られる可能性があります。
これにより、病院の認知度を高めることができるでしょう。
ただし、動画制作には時間と技術が必要です。
高品質なコンテンツを提供するためには、専門のスタッフを配置するか、外部のプロに依頼することが望ましいです。
要するに、YouTubeを活用することで、病院の情報を効果的に広めることができる一方、コンテンツ制作には一定のリソースが必要です。
以下の記事ではクリニックのYouTubeの成功事例について解説しています。

SNS活用が向いている病院の特徴
病院にとってSNS活用が向いているかどうかは、いくつかの要因によって決まります。
- 病院の認知度を上げたい
- 競合医院との差別化を図りたい
- SNSに慣れたスタッフが在籍している
- 広告費用を抑えたい

まず、病院の認知度を上げたい場合、SNSは非常に有効です。
SNSを活用することで、地域の人々に病院の存在を知ってもらい、来院促進につなげることができます。
また、競合医院との差別化を図りたい場合にも、SNSを通じて独自のサービスや取り組みをアピールすることが可能です。
さらに、SNSに慣れたスタッフが在籍している病院は、スムーズに運用を開始でき、効果的なコンテンツを発信しやすいです。
SNSはリアルタイムでの情報発信が求められるため、スタッフがSNSの操作に慣れていることは大きな強みとなります。
そして、広告費用を抑えたい病院にとっても、SNSは低コストで広範囲に情報を届ける手段として適しています。
具体的には、地域のイベントの告知や、専門医の紹介、健康に関する豆知識の発信などが考えられます。
以下で詳しく解説していきます。
病院の認知度を上げたい
病院がSNSを活用する際の一つの目的として、認知度を上げることがあります。
SNSを通じて病院の存在を広く知らしめることで、地域住民や潜在的な患者に対してアプローチが可能です。
特に、地元のイベント情報や健康に関する豆知識、医師の紹介などを発信することで、病院の特徴や強みを広く伝えることができます。
「この病院はどんなサービスを提供しているのだろう?」と疑問に思っている方に対して、SNSはリアルタイムで情報を届ける手段となります。
また、SNSを通じて患者からのフィードバックを受け取ることで、病院のサービス改善にもつながるでしょう。
SNSの特性を活かして、視覚的に訴える画像や動画を活用することで、より多くの人々の目に留まりやすくなります。
結果として、病院の知名度が向上し、患者数の増加にも貢献することが期待できます。
このように、SNSを効果的に活用することで病院の認知度を向上させることができます。
競合医院との差別化を図りたい
競合医院との差別化を図るために、SNSは非常に有効なツールです。
SNSを活用することで、他の病院とは異なる独自の魅力をアピールできます。
例えば、診療の特徴や医師の専門性、最新の医療技術を紹介することで、患者に「この病院なら信頼できるかもしれない」と感じてもらえるでしょう。
また、患者の声や体験談を共有することで、リアルな評判を伝えることができます。
これにより、潜在的な患者に対して安心感を与えることが可能です。
さらに、SNSを通じて地域の健康イベントやセミナーを告知することで、地域社会とのつながりを強化することもできます。
これにより、地域の住民に対して親しみを持ってもらい、選ばれる病院になることが期待できます。
ただし、SNSの投稿内容は常に最新で正確な情報を提供することが重要です。
これにより、信頼性を高め、競合との差別化を図ることができるでしょう。
SNSを活用することで、病院の独自性をしっかりとアピールし、競争の激しい医療業界での差別化を実現することが可能です。
SNSに慣れたスタッフが在籍している
病院がSNSを活用する際、SNSに慣れたスタッフが在籍していることは大きなメリットです。
SNS運用には、プラットフォームごとの特性を理解し、適切なコンテンツを作成・投稿するスキルが求められます。
例えば、Instagramではビジュアル重視の投稿が求められますが、X(旧Twitter)では短文での情報発信が適しています。
SNSに慣れたスタッフがいることで、これらのプラットフォームに応じた効果的な運用が可能となり、病院の情報発信力が高まるでしょう。
また、SNS運用には継続的なコンテンツ制作が必要です。
慣れたスタッフがいることで、投稿の頻度や質を維持しやすくなります。
さらに、SNSのトレンドやアルゴリズムの変化に迅速に対応できるため、常に最新の情報を患者に届けることが可能です。
「SNSの運用に不安がある…」と感じる方も、慣れたスタッフの存在で安心して任せられるでしょう。
このように、SNSに慣れたスタッフが在籍していることは、病院のSNS運用をスムーズに進めるための重要な要素となります。
広告費用を抑えたい
広告費用を抑えたい病院にとって、SNSの活用は非常に有効な手段です。
SNSは無料でアカウントを作成でき、投稿に費用がかかりません。
これにより、限られた予算内で広範囲に情報を発信することが可能です。
「広告費を抑えたいけれど、効果的に情報を届けたい…」と考える病院には理想的な方法でしょう。
SNSを利用することで、ターゲットとする患者層に直接アプローチできるのも大きな利点です。
例えば、特定の地域に住むユーザーに向けて情報を発信することで、地域密着型の広告が実現します。
また、フォロワーとのエンゲージメントを高めることで、口コミ効果を狙うことも可能です。
ただし、SNS運用には戦略が必要です。
単に投稿するだけではなく、どのような内容が患者に響くかを考え、定期的に見直すことが重要です。
広告費用を抑えつつ、効果的な情報発信を目指すためには、計画的な運用が不可欠です。
以下の記事ではクリニックの動画活用ポイントについて解説しています。

病院のSNS運用のやり方・実践ステップ
病院がSNSを効果的に運用するためには、計画的なステップが重要です。
- アカウントを作成する
- 投稿内容を決めてコンテンツの用意
- 投稿する

まず、アカウントを作成し、どのSNSを利用するかを決めることから始めます。
次に、投稿内容を決めてコンテンツを用意します。
ここでは、病院の特色や患者に伝えたい情報を考慮し、視覚的に魅力的なコンテンツを作成することが求められます。
最後に、定期的に投稿を行い、患者とのコミュニケーションを図ります。
SNS運用を成功させるには、ターゲット層を明確にし、彼らが求める情報を提供することが大切です。
また、運用担当者がSNSの特性を理解し、適切なタイミングでの投稿やフォロワーとのやり取りを行うことも重要です。
以下で詳しく解説していきます。
①アカウントを作成する
病院がSNSを活用する際、まず最初に行うべきステップはアカウントの作成です。
これは、病院の公式な情報発信の場を設けるために不可欠なプロセスです。
アカウント作成時には、病院名やロゴを使用し、公式であることを明確に示すことが重要です。
「公式でないと信頼できないかも…」と感じる方もいるでしょう。
公式アカウントであることを明示することで、患者やフォロワーの信頼を得やすくなります。
アカウント作成の際に注意すべき点として、各SNSの利用規約をしっかりと確認し、適切な情報を入力することが挙げられます。
特に、医療情報を扱う際には、プライバシーや個人情報の取り扱いに十分注意が必要です。
また、アカウントのプロフィールには、病院の所在地や連絡先、診療時間などの基本情報を記載し、フォロワーがすぐにアクセスできるようにしておくと良いでしょう。
このように、アカウント作成はSNS運用の第一歩であり、信頼性を確保するための重要な要素です。
②投稿内容を決めてコンテンツの用意
病院がSNSを活用する際、投稿内容の決定は非常に重要です。
まず、ターゲットとなる患者層を明確にし、そのニーズに応じた情報を提供することが求められます。
例えば、小児科であれば子どもの健康に関する情報や予防接種の案内などが考えられます。
また、投稿の目的を明確にすることも大切です。
情報提供を目的とするのか、病院のイメージ向上を狙うのか、集客を狙うのか、それによってコンテンツの方向性が変わります。
次に、コンテンツの形式について考えましょう。
テキストだけでなく、画像や動画を活用することで視覚的に訴求力のある投稿が可能です。
例えば、病院の設備やスタッフの紹介を動画で行うことで、親しみやすさを感じてもらえるかもしれません。
また、季節やイベントに合わせた投稿も効果的です。
インフルエンザの流行時期には予防策を紹介するなど、タイムリーな情報を提供することで信頼感を高めることができます。
最後に、投稿の頻度とスケジュールを決めることが重要です。
定期的な更新はフォロワーの関心を維持するために不可欠です。
無理のない範囲で、週に1回や月に数回といったペースを設定し、計画的に運用することが求められます。
これにより、病院のSNS運用がより効果的に進むでしょう。
③投稿する
投稿する際には、まず適切なタイミングを見極めることが重要です。
SNSの利用者が多い時間帯に投稿することで、より多くの人に情報を届けることができます。
例えば、通勤時間や昼休み、夕方以降のリラックスタイムが狙い目です。
「いつ投稿すれば効果的なのか…」と悩む方もいるでしょうが、これらの時間帯を意識することで効果的な情報発信が可能です。
また、投稿の際には、視覚的に訴えるコンテンツを心掛けましょう。
画像や動画を活用することで、情報がより伝わりやすくなります。
特に健康に関する情報や病院の最新設備、スタッフの紹介など、視覚的に訴える要素を取り入れると良いでしょう。
さらに、投稿後は反応をチェックし、フォロワーからのコメントやメッセージに対して迅速に対応することが求められます。
これにより、患者とのコミュニケーションを深め、信頼関係を築くことができます。
投稿する際のポイントは、適切なタイミングと視覚的訴求、そして迅速な対応です。
これらを組み合わせることで、SNS運用の効果を最大限に引き出すことができます。
以下の記事では各SNSの媒体別運用ポイントについて徹底解説しています。

病院がSNSを始める上での注意点
病院がSNSを始める上での注意点としては、
- 医療広告ガイドラインの遵守
- 施設内のルール整備
が挙げられます。

まず医療広告ガイドラインの遵守です。
医療広告には法律や規則が存在し、これらを守らないと法的な問題を引き起こす可能性があります。
特にSNSでは情報が瞬時に広がるため、誤った情報を発信しないよう、慎重な情報管理が求められます。
また、施設内のルール整備も重要です。
SNS運用に関わるスタッフ間での役割分担や、投稿内容の事前確認プロセスを明確にすることで、情報の誤発信やトラブルを未然に防ぐことができます。
これにより、スタッフ全員が一貫した方針で運用にあたることが可能となります。
以下で詳しく解説していきます。
医療広告ガイドラインの遵守
医療広告ガイドラインの遵守は、病院がSNSを活用する際に非常に重要です。
医療広告ガイドラインとは、医療機関が広告を行う際に守るべき基準やルールを定めたものです。
このガイドラインを遵守しないと、誤解を招く情報が広がるリスクがあり、結果として患者の信頼を損ねる可能性があります。
「SNSで情報を発信するのは良いけれど、どこまでが許されるのか不安かもしれない…」と感じる方もいるでしょう。
具体的には、治療効果を過大に宣伝したり、根拠のない情報を発信することは禁じられています。
また、患者のプライバシーを守るため、個人情報の取り扱いにも細心の注意が必要です。
これらを守ることで、SNSを通じて正確で信頼性のある情報を発信でき、患者との信頼関係を築くことができます。
要するに、医療広告ガイドラインをしっかりと理解し遵守することで、病院のSNS運用はより効果的かつ安全に行えるのです。
医療広告ガイドラインはこちらからご確認いただけます。
施設内のルール整備
施設内のルール整備は、病院がSNSを活用する上で非常に重要です。
まず、SNS運用に関する方針を明確にし、スタッフ全員に周知することが求められます。
「どのような情報を発信すればよいのか」「どのような投稿が禁止されているのか」など、具体的なガイドラインを作成することで、誤った情報の発信や不適切な投稿を防ぐことができます。
また、投稿内容の確認プロセスを設けることも重要です。
たとえば、専門知識を持つスタッフが内容をチェックすることで、医療情報の正確性を確保できます。
さらに、SNS運用担当者の役割や権限を明確にし、責任の所在をはっきりさせることも必要です。
これにより、トラブルが発生した際の迅速な対応が可能になります。
これらのルール整備を徹底することで、病院のSNS運用が円滑に進むでしょう。
以下の記事ではクリニックの動画制作における注意点や成功事例を紹介しています。

病院のSNS運用ならユニセントにお任せ
病院のSNS運用で成功を収めるためには、専門的な知識と経験、そして継続することが必要です。
特に、医療領域の分野は競争が激しく、SNSを活用した効果的な集客戦略が重要になっています。

弊社、株式会社ユニセントでは、SNS特化の動画制作からSNS運用コンサルティングを行っております。
- 独自のブランディングで他社との差別化を図りたい
- より効率的かつ効果的に集客をしたい
- コスパ良く動画を制作したい
- SNSを使用して広告費を削減したい
このようなお悩みを抱えているクリニック様は、ぜひ下記よりお問い合わせください。
https://unisent.co.jp/contact/
今なら初回無料でユニセント代表の長尾が直接ヒアリングさせていただき、あなたのクリニックにマッチしたSNS運用戦略や動画制作のポイントをご提案いたします。
ユニセントは、美容医療業界やクリニックの特性を理解し、それぞれのターゲット層に合わせた動画コンテンツ制作を行います。
4000件以上の動画制作や多ジャンルのYouTubeアカウントを0から数十万人規模の登録者にしてきた実績がございます。
また、データ分析を活用した運用改善も行い、常に最適なSNS運用を実現いたします。
SNS運用でお困りの方は是非お気軽にお問い合わせください。
今なら医療業界向けのSNS運用や動画制作をコスパ良く行う方法が分かるお役立ち資料も無料でダウンロードいただけます。
https://unisent.co.jp/whitepaper/whitepaper-post-01/
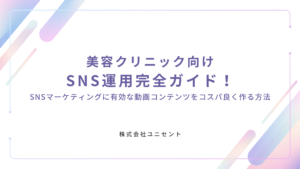
まとめ:病院のSNS活用のメリットとデメリット
今回は、病院のSNS活用に興味を持つ方に向けて、
- 病院がSNSを活用する際のメリット
- SNS活用のデメリットと注意点
- 各SNSの特性と効果的な活用方法
上記について、筆者の経験を交えながらお話してきました。
SNSは病院にとって情報発信の有効な手段です。
患者とのコミュニケーションを円滑にし、信頼関係を築くためには、SNSの特性を理解し、適切に活用することが重要です。
SNSの活用を通じて、病院の存在感を高め、患者との距離を縮めることができます。
まずは、病院に適したSNSプラットフォームを選び、適切な情報発信を心がけましょう。
積極的に取り組むことで、より良い結果が得られるでしょう。
具体的な行動を起こし、病院のSNS活用を成功させましょう。
あなたの成功を心から応援しています。